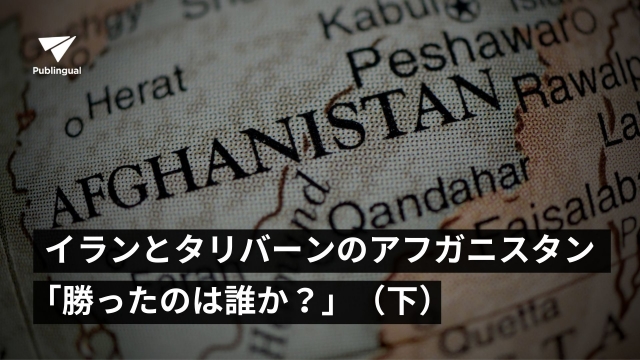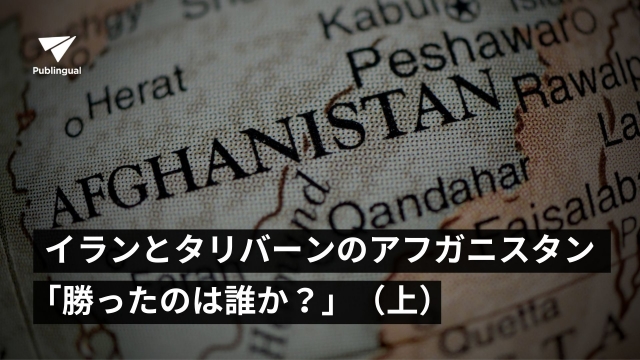この記事の目次
※本稿は、個人的な見解を表明したものであり、筆者の所属する組織の見解を示すものではありません。また、固有名詞のカタカナ表記は一般的な表記に合わせています。
前稿では、イスラム革命(1979年)以降のイランとアフガニスタン(及びタリバーン)の関係について述べた。本稿では、昨年8月のタリバーン復権を受けたイランの対応について、筆者の思うところを記してみたい。
1.勝ったのは誰か?
(1)カブール陥落の衝撃
2021年8月15日のカブール陥落を受け、この状況で得をしたのは誰か?という議論がある。長年タリバーンを背後から支援していたパキスタンや、さらにその後ろに控える中国、タリバーンとの窓口を務めていたカタールなどが「勝ち組」とされ、逆に米国はもとより、インドや民主的な国家作りを支えようとしてきた西側諸国、また単純な評価は難しいが、かつての「北部同盟」側を支援し、イスラム過激主義の伸張を警戒する中央アジア諸国やロシアなどは「負け組」とされる解説を目にした。
では、イランは負けたのか?
状況は複雑である。前稿で述べたとおり、米国のアフガニスタン攻撃により当時のタリバーン「政権」が崩壊したことで、棚ぼた的に漁夫の利を得ていたイランにとり、タリバーンの復活は喜ばしいことでは全くない。
一方で、武力で体制を転覆しうる唯一の存在、超大国米国が東の隣国から消え、さらにこのような「敗走」(ハメネイ最高指導者)を印象づける形になったことは、少なくとも短期的には大きな利益といえよう。米軍を泥沼に足をとらせて疲弊させ、コツコツと抵抗を続ければ、自らの生存圏から大悪魔(米国)を追い払うことができるとの自信を深めた可能性もある。西の隣国イラクでも同様の方策が通用すると考えても不思議はないだろう。
しかし、諸手を挙げて喜ぶことはできない。
これまで米国を始めとする国際社会の多大な投資により、テロの温床とならず、一定の安定が保たれていたアフガニスタンの「パンドラ」の箱が再び開けられ、「力の空白」が生まれることは、イランにとって座視できない事態である。
満員電車の中で座席が空けば、そこに直ぐに腰掛けるか、少なくとも自分の荷物を置くでもしなければ、直ぐに他者(パキスタンやIS―K)に押さえられてしまうからだ。そして、その座席を他者に奪われれば、オセロゲームの隅(角)のように、ゲーム全体の流れを変えてしまうかもしれない。
「アフガニスタンから来るものに、ろくなものはない。」
イラン人がアフガニスタンの影響を語るときに良く聞く言葉だ。難民、麻薬、過激主義の国内への流入、これに新型コロナウイルスも加わった。アフガニスタンが制御不能に陥れば、これらの災いが降りかかってくる。

(2)ランボー3の巨大ブーメラン
『ランボー3 怒りのアフガン』(1988年)を改めて見てみた。主演のシルヴェスター・スタローンが最低主演男優賞に選考された映画であるが、今見ると面白い。
「この映画を勇猛な(gallant)アフガン人たちに捧げる」と、ソ連軍に抵抗するムジャへディン(注:最前線で闘い、生き残った者らの一部が、後のタリバーンの指導者となったといわれる)を称賛するメッセージで締めくくられているのは何とも皮肉である。
「アフガン人は、アレキサンダーもチンギスハンも大英帝国も打ち破った。ソ連も二の舞になるだろう。我々はベトナムの経験があるから分かるのだ」とは、作中のトラウトマン米軍大佐のセリフだが、20年を経て、巨大なブーメランとなって米国に跳ね返ってきたのだ。
「ペルシャ絨毯やイランの細密画を見て御覧なさい。イラン人は「空白」を嫌い、それをどうしても埋めたくなるのよ」

以前に面談したアラブ出身の中東専門家が筆者に述べていた言葉だ。イラン人が「沈黙」を嫌い、その間を埋めようと他愛のない話を続けようとするのも同じ性質なのかもしれない。
しかし、タリバーンが復権したアフガニスタンに対し、イランに、というよりも国際社会にその選択肢は少ない。英国、ソ連、そして米国と「帝国の墓場」であることが改めて証明されたアフガニスタン。米国が抜けた穴を誰も本気で埋めることはできないだろう。中国によるアフガニスタンの資源狙いもあろうが、「力の空白」を埋めることにより利益が得られるとは限らない。筆者の悪友は、「一見早い者勝ちの椅子取りゲームだが、その実、誰も深く腰掛けてはいけないのだよ」と笑った。
別の悪友、イラクやアフガンに勤務経験のある保守系のイラン人ジャーナリストは、「強すぎず、弱すぎない隣国がベスト」と、いつも分かりやすく解説してくれる。イラクにしろ、アフガニスタンにしろ、イランを脅かすほど強大にならず、一方で、内戦などで崩壊するほど脆弱ではなく、親イランの政権か、少なくとも反イランではない体制が維持されることが好ましい。
思えば、9.11後に誕生したシーア派政権の「イラク共和国」も、「アフガニスタン・イスラム共和国」も、イランからの「革命の輸出」が実を結んだといっては語弊があるかもしれないが、イランにとっては心地よく、ほっと一息つける状態だったのではないか。
2.イランの“覇権主義”
(1)革命直後の原体験
革命直後に掲げられた「革命の輸出」という理想や、「被抑圧者の救済に国境はない」とする最高指導者や革命防衛隊の勇ましいスローガンが、中東地域の大国であるイランの図体の大きさと相まって、極めて攻撃的で拡張主義的な国であると捉えられることが多い。
しかし、実際のところ、イランの安全保障戦略は、(少なくともイランから見れば)防衛的で、受動的な側面が強い。東西冷戦のただ中、「東でもない、西でもない、イラン・イスラム共和制!」と東西どちらの陣営にも属さないと高らかに謳って世界初のイスラム革命を成就させるも、その理想が孤立を招き、米国などの西側に支援されたイラク軍の猛攻と、東の隣国アフガニスタンに南下侵攻してきたソ連の脅威に晒され、「祖国防衛」、「革命の体制護持」が最大のプライオリティとなった。
注:ペルシャ湾を隔てた南側では、イランに対抗する組織として、1981年に湾岸協力機構(GCC)が設立された。
この生後間もない時期の原体験が、イランに被害者意識を植え付け、あらゆる事態に反応するための手持ちのカードを増やしてリスクヘッジし、どう転んでも大負けしない方策を模索するに至ったように思える。そもそも、地域大国の域を出ないイランに、地域バランスを一挙に変えるほどの国力はない。敵対する超大国米国の存在もあり、周辺諸外国との均衡を維持するのが先決である。
(2)アフガニスタンでのゲーム
さて、話を再び現代のアフガニスタンへ戻そう。
ここでも、イランは「絶対に大負けしないゲーム」を続けている。ブッシュ大統領による「悪の枢軸」発言(2002年1月)とアフガニスタンにおける米軍駐留を受け、素早い変わり身を見せる。米国排除で利害が一致すると「敵の敵は味方」とばかりに、忌み嫌う仲であったタリバーンに対する武器支援を始め、アルカイダ幹部を国内に匿った。
カブール陥落(2021年8月15日)直後から、イランは、タリバーンとの対話継続と並行して、イスマイルハーンやアフマド・マスウードら反タリバーンのアフガニスタン有力者を国内に匿い、またアブドラアブドラ国家和解高等評議会議長やカルザイ元大統領らとも緊密な連絡をとっている。

「我々は、アフガニスタンの全ての当時者とコンタクトを有している」とのハティブザーデ外務報道官などのイラン政府高官による発言は、決して1点買いはせず、常に逆張り、全通り買いでリスクヘッジをはかるイランのしたたかな生き残り戦術を示している。
イランは、アフガニスタン問題における「キングメーカー」にはなれずとも、発言権・影響力を維持しようと、したたかに足場固めを続けているのである。サッカーにたとえることが好きなイランのシンクタンク所長は、「試合に勝てなくても、試合をめちゃくちゃにすることはできる。つまり、イランは、アフガニスタン問題の解決策にはなれずとも、少なくとも解決を邪魔する“ニュイサンス・バリュー”は維持している」と持論を披露してくれた。
しかし、イラン国内にも微妙な温度差が見られる。カブール陥落の翌日(8月16日)に宗教都市コムで発生した反タリバーン・デモが示すようにシーア派宗教界にタリバーンへの嫌悪感は根強い(注)。また、普段は沈黙しているハタミ元大統領による声明(9月10日)に見られるように改革派・穏健派のタリバーンに対する警戒感は今も健在である。
注:米国のメリーランド大学が昨年実施した世論調査「IranPoll」によれば、88%のイラン人回答者が「タリバーンを好ましく思わない」と回答したとしている。
一方で、革命防衛隊は、「タリバーンの再登場」という現実を受け入れる用意を着々と進めているようである。「今日のタリバーンは、2000年当時のタリバーンと大いに異なっている。タリバーンとISの思想は完全に異なっている。」(10月12日、ニールフォルーシャーン革命防衛隊作戦担当副司令官)といった防衛隊幹部の発言はイラン国内の反応を探る観測気球のように見える。
10月17日、筆者の目を引く人事が発表された。
ライースィ政権は、アフガニスタン問題担当を外相特使から大統領特使に格上げし、故ソレイマニ司令官の腹心であったカーゼミ・ゴミ氏を任命した。ゴミ特使は、革命防衛隊コッズ部隊の出身であり、かつてのタリバーン「政権」下でイランの特別代表を務めたほか、イラク大使、(アフガニスタンの)ヘラート総領事を歴任している強者(つわもの)である。
2010年にイラクに着任した筆者には、ゴミ氏との直接の面識はないが、同氏は駐イラク大使(2005年~2010年)を辞した後も、「バグダッドのイラン大使館の地下に住んでいる」との噂が立つほど、神出鬼没にイラク国内に現れ、イラン・イラク関係のキーマンといわれていた。それだけに、同氏のアフガニスタン特使任命は、イランによるアフガニスタン問題への本気度を感じさせるものであった。
ゴミ特使は、任命翌月の11月15日から早速アフガニスタンを訪問し、タリバーン指導層(バラーダル第一副首相、ハナフィ第二副首相、ムッタキ外相代行)と面談する一方、現地でのインタビューに応じ、(イラクやシリアでの経験に言及した上で)「アフガニスタンにおけるISの攻撃は「真の代理戦争」であるとし、その背後には米国とシオニスト(イスラエル)がいる」と非難した。筆者に目には、ISとその背後にいる米国とイスラエルを「不変の敵」として据え、現実問題としてのタリバーンを受け入れるという意思表示に映った。
それに先立つハメネイ最高指導者の発言も見逃せない。カブール陥落後間もない8月28日、ハメネイ師は、「我々はアフガニスタン国民の支持者である。なぜなら、これまで同様に(アフガンスタン)政府はやってきて去って行くが、国民は残り、イランとアフガニスタン政府の関係は、同国民とイランとの関係によるからである」と述べ、タリバーンを受容するかのようなニュアンスを醸し出している。革命防衛隊の動きも、このような最高指導者の意図に沿ったものであろう。
(3)ペルシャ帝国の版図(はんと)
YouTubeで面白い動画を見つけた。かつてのペルシャ帝国の影響圏をさかのぼると、東方への伸張は限定的で、基本的には西へ西へと拡がっていたと指摘している。これは、イランのザグロス山脈を越えた西方には平地が広がっていたことなど、主に地理的な要因を解説したものであるが、現代イランにおいても、イラク、シリア、レバノンと、その先にある宿敵イスラエルに対抗する戦略的な重要性や、イラクとの国境周辺に広がる石油埋蔵地域の確保の観点からも、西の国境防衛、そのための西方への伸張・浸透がより重視されているように見受けられる。
「大詰め」とされる核合意(JCPOA)交渉や緊迫するウクライナ情勢もある中、今後、イランが、東方でのタリバーン復権という現実に対処し、また西方での変化(イラクでの駐留米軍の戦闘任務完了(2021年12月10日)や昨年10月の総選挙による親イラン勢力の退潮等)にどのように対応していくのか、引き続きイランからウォッチしていきたい。
▶イランとタリバーンのアフガニスタン:「勝ったのは誰か?」(上)
(寄稿:角 潤一(在イラン日本国大使館 一等書記官)、編集・デザイン:深山 周作)