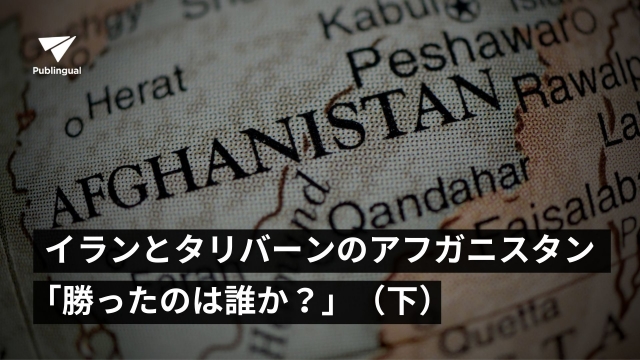※本稿は、個人的な見解を表明したものであり、筆者の所属する組織の見解を示すものではありません。また、固有名詞のカタカナ表記は、一般的な表記に合わせています。
「グランドバーゲン」は可能か?
バイデン政権誕生後、進展が期待された米・イラン関係は、JCPOA(イラン核合意)のコミットメントを巡り、イランは米国に対して制裁解除を、米国はイランに対して核開発の制限を求め、どちらが先かの差し手争いが続いている。
さらに、米国はこの合意を核問題に限らず、地域問題や弾道ミサイル開発など、よりスコープを拡げた新たな交渉の「出発点」としたいとしており、イランは警戒を強めている。
こうした中、ふと、かつて幻となった「グランドバーゲン」が筆者の頭をよぎる。
これは、2003年、イランが米国との関係改善に向け、核開発のみならず、大量破壊兵器(WMD)、テロやイラク、中東和平(ハマス、ヒズボラ)などの広範な内容を含む包括的な提案(グランドバーゲン)(※参考:Iran’s Proposal for a ‘Grand Bargain’ – The New York Times)を行ったが、当時のブッシュ政権により門前払いされた、というものである。
もっとも、米・イラン両国政府関係者はこの提案の存在を公式には認めていない。
今、このような広範なディールが成立する可能性があるだろうか?
当時のイランを取り巻く状況は、現状とは大きく異なる。
時計の針を20年戻してみよう。
9.11後の世界
2001年9月11日、ニューヨークのワールドトレードセンターに2機目の航空機が突っ込んでいくのを、筆者はテヘランの自宅アパートのテレビで見た。
「あのテロリストたちの中に、イラン人がいませんように!」
当時学生だった友人たちの祈りの言葉だ。日本大使館(当時)にほど近いアルゼンチン広場には、学生や若者たちが大勢集まり、キャンドルを灯して犠牲者に哀悼の意を表した。(注:実際、実行犯の中にイラン人はいなかった。)
この事件を契機に、米国では「新保守主義(ネオコン)」 が勢いを増すことになるが、イランは「米国が何らかの口実を見つけて攻撃してくるのではないか」と神経を尖らせていた。
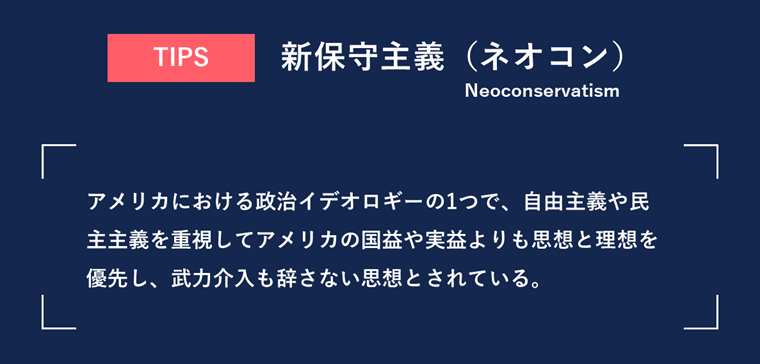
米国は、同時多発テロの実行犯であるアルカイダ(AQ)を匿っているとして、タリバンが実効支配していたアフガニスタンを攻撃(2001年12月)、続いて大量破壊兵器を保有しているとしてサダム・フセインのイラクを攻撃(2003年3月)し、両国の体制を転換(regime change)した。
タリバンと敵対するイランは、アフガニスタン戦争において米国との事実上の協調関係(AQ幹部の居場所などの情報提供等)を結ぶが、ブッシュ大統領の「悪の枢軸」演説(2002年1月)により梯子を外されてしまう。

そして、8年間戦っても決着をつけることができなかった(1980年~88年、イラン・イラク戦争)宿敵サダム・フセインをあっという間に蹴散らした米国の軍事力をまざまざと見せつけられ、イランは「次は自分たちの番だ」と強い恐怖心を抱く。
さらに、イラン反体制派のモジャヘディネ・ハルグ(MKO)による暴露(2002年8月)が発端となり、イランの秘密裏の核開発への疑惑が急浮上していた。
このように「イスラム革命体制の護持」を最重要事項とするイラン指導部は、当時、相当な圧力に晒されていた。
先の真偽不明のグランドバーゲン提案は、こうした状況下で生まれたものであった。
では、現状はどうであろうか?
その後、アフガニスタン・イラクの両戦線は泥沼化、米軍の死傷者が増えるにつれ、米国民には厭戦感が漂い、米軍の縮小・撤退論が強まっていく。そして、2013年9月、オバマ大統領が「米国は『世界の警察官』を辞める」と宣言するに至る。
従来、中東地域は、イランのほか、サウジアラビアやイラク、トルコ、イスラエルなどが、時に米・英など域外国の支援を得ながら、互いに牽制し合い、微妙な「力の均衡」を図ってきていた。
しかし、奇しくも、米国の対テロ戦争により、イランの東西の宿敵が排除されたことで、アフガニスタンとイラクに「力の空白」ができ、イランが手足を伸ばすスペースが生まれた。このスペースを地域諸国はそれぞれの思惑から埋めようとしたが、最も準備ができていたのはイランだった。
もともとペルシャ語文化圏であるアフガニスタンはイスラム共和国(2004年)となり、イラクにはイランの国教であるイスラム教シーア派の政権が樹立(2006年)された。
イランは、米軍がアフガニスタン・イラクの両戦線で身動きがとれなくなっているのを見て、もはや大規模な地上軍をイランに投入し、イランの体制を転覆する余裕はないと見るようになる。
たしかに、現在のイランは、トランプ前政権による「最大限の圧力」政策の下で科された史上最強の経済制裁に苦しみ、さらに未曽有のコロナ禍が追い打ちをかけている状況にある。
しかし、体制転覆の危機に恐れおののいていた当時とは、イラン体制指導部が感じる切迫度が全く違うのである。
では、米・イラン間の合意の望みはないのだろうか?最近のイランの動きを見てみよう。

バイデン政権誕生後も、金属ウランの製造開始(2月8日)、未申告の核施設などへのIAEAの査察等を認めた「追加議定書」等の履行停止(2月23日(注))、より高性能なIR4型遠心分離機を連ねたカスケードへのウランの供給開始(3月15日)と、矢継ぎ早に核合意に反する核開発活動を進めている。(注:IAEA事務局長がテヘランを訪問し、2月21日、イランとの共同ステートメントを発出。3か月間を限度として、必要な検証・監視活動を継続するための技術的な了解を取り付けた。)
イランのアラヴィ情報相は、核兵器はイスラム法に反するとのハメネイ最高指導者の言葉に触れつつも、イランを猫にたとえて「追い詰められれば違った行動を取らざるを得ないかもしれない」と述べ(2月9日)、最高指導者も「必要なら60%までウランを濃縮する」と発言する(2月22日)など、揺さぶりをかけている。
また、イランは今年に入り、国内の砂漠地帯やオマーン湾、インド洋を含む広範な地域で次々と軍事演習を行っており、2月中旬にはイラン・ロシア海軍の合同軍事演習を実施。また、イラン国防軍需省は、2月1日、人工衛星打ち上げ用の新型国産ロケット発射実験に成功したと発表した。(注:そのほか、ペルシャ湾での韓国籍タンカーの拿捕(1月4日、イラン側は同タンカーによる環境汚染が理由と説明)や、イランの関与は不明であるが、インドのイスラエル大使館付近で爆発事件(1月29日)、オマーン湾でイスラエル企業所有の船舶爆発事案(2月25日)、イエメンの親イラン武装組織フーシ派によるサウジアラビアへの攻撃などの不穏な動きもある。)
こうしたイランの動きの意図を、どのように見ればよいのだろうか?
トランプ政権による「最大限の圧力」をイランは「戦略的忍耐」でしのぎ、米国の一方的な核合意離脱に対しても、最初の1年間は核開発活動を抑制するコミットメントを維持していた。しかし、こうした「モラルハイ」な立場(注)を捨て、イランがいよいよ攻勢に出てきた感がある。(注:イラン自身は核合意のコミットメント(核開発活動の制限)を遵守している中で、同合意から一方的に離脱しイランに制裁を科す米国を非難し、また無力な欧州諸国を批判できる立場。)
こうしたイランの動きを、西側、とりわけ米国の気を引くための「瀬戸際外交」「かまってちゃんポーズ」と評する悪友もいる。
しかし、実際、これらは、前回の寄稿で触れた某政策シミュレーションで、筆者がイランの最高指導者役を務めた際、事態を打開するためにとった策とほぼ同じである。イランとしては、交渉にできるだけ強い立場で臨めるよう、使える「カード」を集めている状況ではないだろうか。
先のイランの核開発活動を加速する法律について、ガリバーフ国会議長は「力の創造」、ラリジャニ最高指導者顧問は「イランの力のツール」と述べ、またザリーフ外相は、貯蔵量が2.9トンにまで達した濃縮ウランこそが制裁への対抗策であり、イランのパワーであると述べている。
ハメネイ最高指導者は、1月8日の演説において、「我々の要求は制裁解除である」と核合意に対する姿勢を明確にしており、恒例のノウルーズ(イラン正月、3月21日)に際しての演説でも、対米不信をあらわにしつつも、「米国は全ての制裁を解除しなければならない。本当に制裁が解除された場合には、我々は一切の問題なく、核合意に戻る」と核合意の存在を前提とした発言をしている。
また、当初、米側に要求していた(イランが経済制裁により被った)損害の賠償についても、「制裁解除の後で」とトーンダウンしている。
バイデン政権が求めていた核合意復帰を巡る対話について、「時期尚早」としてイランは拒否(2月28日)したが、これも交渉を優位に進めるための戦術かもしれない。3月初旬の現地発の報道では、イランが「建設的な行動計画を提案する」「核合意の正常化に向け、米国の制裁解除とイランの核開発制限を同時並行で段階的に進める新提案を、近く欧州連合(EU)を通じて提示する」といった見通しも浮上している。
交渉の主導権を握る上で、ペンホルダー(起案者)になることは極めて重要だ。ロウハニ大統領も、「相手側が核合意上の義務を部分的に履行すれば、それに対してイラン側も部分的な履行を行う」と述べている(3月10日)。
実際の交渉入りのタイミングは別として、少なくともイラン側の準備は徐々に整いつつあるのではないか。
イラン国内に根強い対米不信に加え、米国の国内事情やサウジアラビアやイスラエルなどの反イラン陣営の思惑など、米国の核合意復帰、米・イラン間の対話を阻む問題点を挙げればきりがないが、ここでは、あえてより楽観的なシナリオの可能性を考えてみたい。
まず、少なくとも、一度は合意したJCPOAというベースが残っており、米国もイランも、JCPOAのコミットメントに戻るようにと相手側に求めており、その軸は定まっている。
現在の主要な焦点は「どちらが先か」というプロセスの問題であり、第3国による仲介や、一旦双方がこれ以上のエスカレーションを停止するダブルフリーズ、同時並行で段階的に進めるロードマップの策定など、外交が知恵を出せる余地はあるのではないだろうか。
両国間の信頼醸成に向け、双方の善意を示す上では、たとえば、米側からは人道支援としてコロナ危機に対処するための国際通貨基金(IMF)の借款の検討、イラン側からは拘束中の米国籍者の解放などがあるかもしれない。(注:バイデン政権は、既に、米イラン間の交渉の舞台であるNYにおけるイラン外交官の移動制限の緩和、対イラン国連制裁が復活(スナップバック)したとのトランプ政権時代の主張の撤回などを実施。また、サリバン米大統領補佐官(国家安全保障問題担当)は、2月21日、イランで拘束されている米国人の解放に向けて「イランとの連絡を始めた」と発言している。)
もう一つの焦点である、「スコープ」については、最初から核問題以外の事項を交渉対象に含めることは極めて困難であろう。しかし、核合意に復帰した後、たとえば、アフガニスタンやイエメンなど個別の地域情勢についての対話を行うことは可能であろう。これはザリーフ外相も複数のインタビューで示唆している。
アフガニスタンについては、過去にも対話の実績があり、また最近の報道によれば、ブリンケン米国務長官からアフガニスタンのガニ大統領への書簡で提案された内容には、イランを含めた関係国の対話の枠組みがあるとされている。1月末には、イラン外務省の招待を受けたタリバン代表団がイランを訪問している。
イエメンについては、バイデン政権は、反政府勢力フーシ派のテロ組織の指定の解除や、サウジアラビア主導の連合軍に対する軍事支援を停止する方針を表明しており、イラン外務省報道官は「政治的な駆け引きでなければ、過去の過ちを正す一歩になる可能性がある」と前向きに捉える考えを示している。また、2月はじめにグリフィス・イエメン担当国連事務総長特別代表がイランを初訪問したことも注目される。(注:ただし、弾道ミサイル開発はイランにとり国防の肝であり、2003年の幻の「グランドバーゲン」にも含まれていなかったことには留意が必要である。イランのハタミ国防軍需大臣は、3月18日、ミサイル能力の強化を断固として進めていく意向を示している。)

イランにおける今後の注目すべきタイミング
イランの大統領任期は最大2期8年。今年はイランにとり、JCPOAをまとめたロウハニ政権(穏健派、2期目)が退陣し、8年ぶりに新たな大統領を選ぶ「政治の年」となる。イランの政権は、人々の現状打破への期待とそれが裏切られたことへの失望のサイクルを背景に、改革派・穏健派と強硬派の間をスイングしており、順当にいけば次は強硬派が政権を奪取する番である。
制裁とコロナ禍により疲弊した経済の立て直しが選挙の主要な争点になると見られており、「制裁解除」という成果を誰が達成するのか、任期切れが迫るロウハニ現政権と、政権奪還を目指す強硬派との間での綱引きも激化してきている。
現在、イランは3月中旬から4月初旬にかけて、ノウルーズ(イラン正月)の新年休暇モードに入っている。その後に続くラマダン(断食月。4月12日頃~5月12日頃)が明けると、いよいよ大統領選挙(6月18日投票)に向け、具体的な候補者の顔ぶれが明らかとなり、国内は一気に選挙モードへ突入していく。(注:5月11日~15日が候補者登録期間であり、5月下旬から20日間程度が選挙キャンペーン期間となる。新大統領の就任は8月頃。)
また、5月21日頃には、先述のイランとIAEA間の技術了解の期限を迎え、制裁解除に前向きな進展がなければ、イランの核開発活動に対する十分な監視活動ができなくなる恐れがある(6月にはIAEA定例理事会が予定されている)。
この短い時間的なスロットの間に、米・イラン間で、とりわけ核合意を巡り、何らかの動きが出てくるのか、それとも夏以降に持ち越されるのか、イランの大統領選挙の趨勢にも大きな影響を与えうるものであり、注目していきたい。(※注:イラン大統領選挙については、稿を改めたい。米大統領選挙とイランの大統領選挙の関係については、拙稿「抵抗か協調か、イランの民意を左右する米大統領選 半年遅れで訪れるイラン大統領選に注目すべき理由|JBpress 」を参照下さい。)
(寄稿:角 潤一(在イラン日本国大使館 一等書記官)、編集・デザイン:深山 周作)