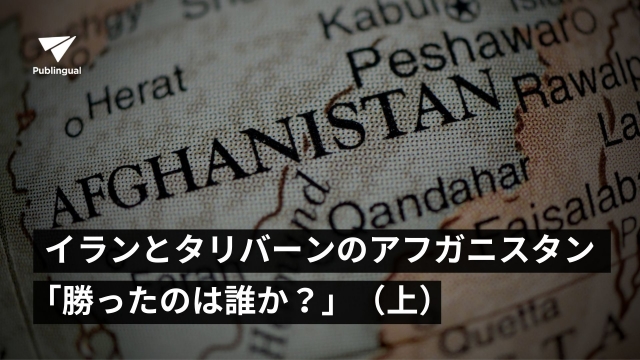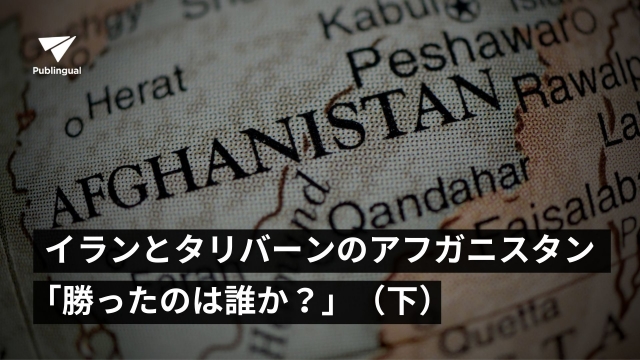※本稿は、個人的な見解を表明したものであり、筆者の所属する組織の見解を示すものではありません。また、固有名詞のカタカナ表記は一般的な表記に合わせています。
カブール陥落から半年あまりが過ぎた。
実は、昨年夏、アフガニスタンについて何か発信しようと執筆を始めたものの、長く足が遠のいてしまっている国でもあり、また、現地の友人・知人の状況が気がかりで、結局筆を置いてしまっていた。
最近は、ウクライナ情勢にかき消されて日本のメディアで取り上げられる機会が減りつつある気もする。アフガニスタンの国内情勢やタリバーンについてはより専門の方々にお任せし、あくまで現地での限られた個人的な経験をベースに、今回も「イランからの目線」で書いてみたい。
まず、本稿では、イスラム革命(1979年)以降のイランとアフガニスタン(及びタリバーン)の関係に触れ、次稿では、昨年8月のタリバーン復権を受けたイランの対応について記す。
1.私のアフガニスタン
アフガニスタンは筆者にとって思い出深い国だ。2001年9月11日、ニューヨークの世界貿易センタービルに旅客機が突っ込んだ時、私はテヘランに居た。翌10月に米英軍によるアフガニスタン攻撃が開始され、11月、タリバーンは首都カブールから撤退した。
筆者が初めてアフガニスタンの地に足を踏み入れたのは、その翌月、12月22日にハーミド・カルザイ氏を議長とする暫定政府、アフガニスタン暫定行政機構が成立した直後だった。ソ連軍が残した空港跡、バグラムには何もなく、カブール市内も混沌としていた。

テヘランでの語学研修を終えたばかりの筆者にとり、本格的な通訳(ペルシャ語)デビュー戦は、その後大統領となるカルザイ議長と、タリバーンが去った直後のカブールを訪れた日本の政治家との会談だった。「部族的な重みがない」などと評されるカルザイ氏であるが、気さくで、アフガン伝統衣装であるチャパンとカラコル帽をおしゃれに着こなす、西欧的な香りがする人物だった。

その後、テヘランから志願してカブールの日本大使館へ異動したのが2004年。ボン会合、東京会合を経て、アフガニスタンの復興支援の機運が盛り上がっていた時期に、経済協力班員として、マザリシャリフ、ヘラート、バーミヤン、カンダハール、ジャララバードと、2年間、比較的安定していた治安の中、ほぼ全州、国中を走り回った。
筆者も初期の復興に携わったカブール国際空港が、国を脱出しようとするアフガン人で溢れかえり、米軍機にしがみついた者が空から降り、また大規模なテロの標的となったことには言葉が出ない。
2.イランとアフガニスタン
(1)隣国イランは「仰ぎ見る大国」
9.11テロ事件から20周年を迎えた昨年9月11日、映画『ミッドナイト・トラベラー』を渋谷で観た。
タリバーンから死刑の警告を受けたアフガン人家族が3台のスマホで自らの欧州までの旅を撮影したセルフドキュメンタリー。5600kmにも及ぶ旅のなかで、筆者の最も印象に残ったのは、一瞬だけ映し出されたイランでの様子、アフガニスタンからの脱出に成功し、コム周辺と思われるきれいに舗装された道路を走る車窓から、「最高の気分だ!」と一家が笑顔を見せる瞬間である。アフガニスタンの人々にとり、隣国イランは「仰ぎ見る大国」である。イランとアフガニスタンの国境に立つとその違いは際立つ。国の隅々まで電気が行き渡り、舗装道路が広がるイラン側と、何もない荒野と土漠が続くアフガニスタン側。

2年間のアフガニスタン勤務で、筆者が一番覚えているのはとにかく寒かったことである。厳しく冷え込む冬、停電は日常であり、庭先に設置した巨大な発電機は直ぐに故障し、またそれを動かすための燃料も不足していた。
文化的にも「ペルシャ」への憧れを感じた。カブールの日本大使館に勤めていたアフガン人スタッフは、筆者のテヘラン訛りのペルシャ語を「イラン映画やテレビで聞いたのと同じ響きだ!」とある種の羨望を示し、「ダリー語ではこう言うが、ペルシャ語で何と言うのか?」などとよく聞いてきたものだった。
一方で、長く続く乱世を生き抜いてきたイスマイルハーンやアタ・モハンマド、ドスタムなど、現地で直接やりとりしたこともある軍閥の長たちは、筆者にとりわけ強い印象を残している。金(かね)や力が全て、裏切りの連続であったのだろうか。笑顔の中にも、決して笑わない目、その奥に戦慄を覚えるような光を宿していた。
(2)革命後のイランとアフガニスタン
髙橋博史元駐アフガニスタン大使は、複雑なアフガニスタン情勢を解説するために、16世紀のサファヴィ朝(イラン)、シェイバーン朝(ウズベク)、ムガール帝国(インド)の争いにまで遡っていらしたが、本稿では、一気にイスラム革命当時(1979年)まで飛ぶことにする。
今回の執筆にあたり、革命後のイランの東西での主な出来事をざっと書き出してみた。
俗に「10年周期説」などとも呼ばれるが、中東地域はほぼ10年に1度、世界を揺るがす大事件の震源地となっている。1980年のイラン・イラク戦争、1990~91年の湾岸危機・戦争、2001年の米中枢同時テロ(その後のアフガン、イラク戦争)、2010年12月以降の「アラブの春」。そして、昨年2021年8月15日のカブール陥落。
さらに、イラン目線で言えば、これらに1~2年先立つ形で、1979年のイスラム革命が成就(注)、以降、1989年のホメイニ師死去、1999年のテヘラン大学襲撃事件、2009年の「グリーンムーブメント」、2019年の全国的な反体制デモなど、イランの体制の根幹を揺るがしかねない事案が起きている。
注:これに先立つ1978年4月、アフガニスタンでサウル(4月)革命(共産革命)が起きる。これがイスラム過激主義のグローバル化(国家破綻による暴力の拡散)の発端となったとの指摘もある。
産声を上げたばかりの革命イランの東西は激動していた。東ではソ連によるアフガニスタン軍事侵攻(1979年12月)、西ではサダム・フセインのイラクとの間でイラン・イラク戦争が勃発(1980年9月)。
イランは、アフガニスタンを経由して国内に共産主義が押し寄せることを警戒すると同時に、革命を東へ輸出する機会と捉え、アフガニスタンのシーア派勢力支援に乗り出す。一方、イランの「革命の輸出」を恐れた西の隣国イラクによる「戦争の押しつけ」は、イランにとり、革命直後の国内の混乱や不和を、「国土防衛のため」として一致団結させるのに役立った。
1988年8月、8年間におよぶ泥沼のイラン・イラク戦争が終結し、翌年1989年2月にソ連軍がアフガニスタンから撤退する。同年6月にイスラム革命を導いた初代最高指導者ホメイニ師が亡くなると、イランはハメネイ・ラフサンジャニ体制へ移行し、より現実・実利主義の外交へとシフトしていく。
アフガニスタンでは、共通の敵ソ連を追い払った後、各勢力の寄せ集めであったムジャヘディンによる内戦へと突入する。イランは、主として、宗派つながりのあるハザラ民族(シーア派)に対する支援を通じて自らの影響力を維持しようとする。
そのような乱世の中、1994年、ある種の「世直し運動」として出現したのがタリバーンであった。1996年、タリバーンは、アフガニスタンを実効支配(翌97年10月に「アフガニスタン・イスラム首長国」に名称変更)し、実質的な首都機能をカンダハールに据えた。少数派ハザラを含む北部同盟を支援していたイランにとり、タリバーン「政権」の登場は痛手であった。
(3)イランとタリバーン
どちらも「厳格なイスラム主義」として「同じようなモノ」としてざっくりと捉えられてしまうかもしれない。しかし、両者はイデオロギー的には水と油であり、シーア派を異端視するタリバーンにとり、シーア派大国イランは忌み嫌う敵であり、逆にイランにとっては900km以上もの国境を共有する東の隣国でそのようなグループが権力を掌握したことはゆゆしき事態であった。革命イランの波及を恐れたサウジアラビアが、パキスタンのマドラサ(神学校)を支援し、「反シーア」、「反イラン」をより強く植え付けたとの指摘もある。
スンニ・シーアの宗派間の対立を別にしても、両者はもともと「犬猿の仲」である。田中浩一郎氏は、タリバーンによる反イラン主義の源泉を、パシュトゥーン民族主義が根底にあり、18世紀にサファヴィ朝とドゥッラーニー朝(現在のアフガニスタンにおける国家の基盤)が領土の奪い合いをして以来の怨念にまで遡ると指摘されていた。パシュトゥーン・ワリー(部族の慣習法)の重要な要素の一つとして、「復讐(バダル)」があり、損害を被った場合、何世紀を経ようとも復讐を企て果たすまで諦めることはない、と青木健太氏は書かれているが、筆者の対面したアフガン軍閥の長たちにも、そのような執念深さが感じられた。
1998年8月8日、両者の対立は頂点を迎える。
北部の要衝であるマザリシャリフを制圧したタリバーンがイラン総領事館を襲撃し、イラン人外交官8名とイラン人記者1名を殺害した。ハメネイ最高指導者はタリバーンとの軍事衝突の準備を整えることを国民に示唆し、イランは20万ともいわれる兵力を国境に配備した。緊張は「戦争直前」にまで高まったが、最終的に、ハタミ政権(改革派)下のイランはギリギリのところで押し留る。しかし、23年以上がたった今でも、毎年8月8日にはイラン外務省で追悼を続けており、「あの日のことを決して忘れることはない」と述べるイラン外務省のベテラン職員は少なくない。
ガーセム・ソレイマニの登場も、この時期に重なる。

イランのイスラム革命防衛隊(IRGC)研究の第一人者であるアリー・アルフォネ(Ali Alfoneh)氏は、革命防衛隊はタリバーン弱体化のために多大な労力を費やしており、それを如実に表しているのがソレイマニのコッズ部隊司令官指名(1998年頃)であると述べている。同氏は、ラフサンジャニ大統領の回顧録をひもとき、1999年2月、ソレイマニ司令官が当時の外務省によるタリバーンとの交渉を、(イランが支援する)ムジャヘディンのモラルを低下させるものであると批判していたと指摘している。
しかし、このような革命防衛隊のタリバーンに対する脅威意識と対応が、その後の国際情勢によって大きく変わっていく様は興味深い。
次の大きな転機は9.11(2001年9月11日)。同事件を引き起こした国際テロ組織アルカイダ(AQ)の指導者オサマ・ビンラディンを匿っているとして米軍の攻撃を受けたタリバーン「政権」は、瞬く間に崩壊した。この際、ソレイマニ司令官らが米側に水面下で協力していたことは公然の秘密である。
「グレートサタン(大悪魔)」(米国)の快進撃により、東の隣国アフガニスタンのタリバーンも、かつて8年間戦っても決着がつかず、「毒杯を飲む」(ホメイニ師)ほどの苦渋の決断で停戦した西の隣国イラクのサダム・フセインも、あっという間に蹴散らされ、東西の宿敵を退治してもらったイランは、棚ぼたの安全保障上の利益を得た。
しかし、同時に、この時ほど「次こそは自分たち(イラン)が殺(や)られる番だ」という危機感を抱いたことはないだろう。当時テヘランに最初の駐在中だった筆者も、そのような雰囲気をひしひしと感じた。9.11は、米軍基地が自国の東西隣国両国に陣取るという(イランにとっての)大きな負の遺産を残した。
注:この時期には、国外のイラン反体制派により、イランの秘密裏の核開発活動が暴露(2002年8月)され、また「グランドバーゲン」と呼ばれた幻の提案がイランから米国に打診された(2003年)といわれる。
イランの変わり身は素早い。米軍によるアフガニスタン駐留直後から、イランは積極的にタリバーンに支援を行うようになったといわれる。2002年1月のブッシュ米大統領による「悪の枢軸」発言が引き金になったとの指摘もある。
イランは、東西からの米軍による攻撃を封じるため、イラクでは親イラン組織(注:フセイン政権時代にイラン国内に匿っていたイラク人が主導する組織等)に、アフガニスタンではタリバーンに対して武器支援などを開始し、非対称戦・代理戦争により米軍を弱体化させる手法を採るようになる。
さらに、2015年のIS―K(アフガニスタンのIS系組織「イスラム国ホラサン州」)の台頭を受け、イランは、アフガニスタン政府の統治能力の限界を悟り、タリバーンとのよりハイレベルの接触を始めたとされる。イラン外務省のムサヴィ南アジア担当次官補もインタビューで、2016年頃からアフガニスタン政府側からの要望に基づき、タリバーンとの対話を行っていることを認めている。
**********
このようなイランの布石は、昨年夏の衝撃のカブール陥落を受け、どのような意味を持つのだろうか。次稿では、タリバーンの復権を受けたイランの対応を見ていきたい。
▶イランとタリバーンのアフガニスタン:「勝ったのは誰か?」(下)
(寄稿:角 潤一(在イラン日本国大使館 一等書記官)、編集・デザイン:深山 周作)