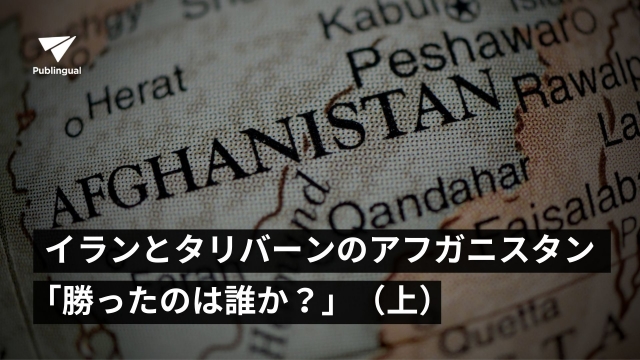この記事の目次
※本稿は、個人的な見解を表明したものであり、筆者の所属する組織の見解を示すものではありません。また、固有名詞のカタカナ表記は一般的な表記に合わせています。
イランに潜伏するクロコダイル

紫のスカーフで金髪を覆った長身の女性が、テヘラン郊外のイマームホメイニ空港に到着する。彼女は、ペルシャ語はもとより、イランに関するあらゆる知識を完璧に叩き込まれた英国秘密情報部:MI6のエージェントだ。英国大使館の「臨時代理大使」という肩書きを隠れ蓑に、イランへ密かに送り込まれて来た。しかし、彼女の動向は、イラン・イスラム革命防衛隊の諜報部隊に完全に掌握されていたのである。
これは、イラン国営放送の人気スパイ・スリラー『Gando(ガンドォ)』(注1)のシリーズ第2作13話の内容だ。しかし、このエピソードの放送(4月2日夜)を最後に突然の終わりを迎え、「続きは大統領選挙後まで持ち越し」とされたことで、国内外の“イラン・ウォッチャー”の注目を集めることになる。筆者も慌てて全作品(43話)合計1,935分間を見直した。
(注1:イラン南東部の沼地などに生息するワニ(mugger crocodile)のペルシャ語名。)
イラン大統領選挙におけるメディアの役割:空前の「空中戦」か?
前回の拙稿では、6月の大統領選挙までの限られた時間的スロットの中で、米・イラン間で、特にイラン核合意(JCPOA)を巡り何らかの動きが出れば、選挙の趨勢に大きな影響を与えうると指摘した。実際、4月6日以降、ウィーンにてイラン核合意の再生に向けた交渉、米国との「間接協議」が断続的にだがハイペースで続いている。

イラン大統領選挙(6月18日投票)まで、約1か月となったが、候補者登録(5月11日~15日)、憲法擁護評議会による資格審査(後述)を経て、大統領候補が出そろうのは5月27日頃とされており、選挙キャンペーン期間はわずか2週間半(5月28日~6月16日)の超短期決戦となる。つまり、5月末までは「出走する馬すら分からない状況」なのである。
このような中で、核合意再生による制裁解除を勝ち取り、現状では劣勢とされる大統領選挙への起死回生を狙うロウハニ現政権(穏健派)と、それを断固阻止したい強硬派勢力のせめぎ合いが表面化してきている(注2)。
(注2:イラン国内における政治対立は複雑であるが、本稿では、その基本的な理解のために、核交渉に代表される諸外国との国際協調を志向するグループ(いわゆる「穏健派」,ロウハニ大統領の現政権)と、西側諸国、とりわけ米国・英国などに対する不信感が強く、国内の潜在能力の活用により外圧に対抗することを志向するグループ(いわゆる「強硬派」、国営放送、革命防衛隊、司法権など)に単純化して議論をすすめたい。)
このダイナミズムを理解する一助として、今回の寄稿では、イランの大統領選挙について、「メディアの役割」という切り口で書いてみたい。筆者は、新型コロナウイルス感染症の蔓延により、大統領候補が実際に地方遊説や支持者を集めた大集会の開催などといった「地上戦」が展開できない中、インターネットやメディアの役割はかつてないほど高まり、空前の「空中戦」になるのではないかと予想している。

まず、イランにおける大統領選挙そのものの位置づけを簡単に紹介した後、既存のマス・メディア、とりわけ国営放送(強硬派)とロウハニ現政権(穏健派)との戦いを取り上げ、次稿では、「Twitter革命」と呼ばれた2009年の大統領選挙から現在の「Clubhouse」の登場など、イランの大統領選挙におけるソーシャル・メディアの役割について紹介してみたい。
イランの大統領選挙
イランの強硬派は、彼らの牙城である「司法権」(ライシ司法権長)に加え、昨年2月に大勝した国会選挙で「立法府」(ガリバフ国会議長)を手中に収め、既に3権の長のうちの2つを抑えており、残る「行政府」(ロウハニ大統領)の8年ぶりの奪取を虎視眈々と狙っている。
強硬派にとり、実際には選挙戦があまり盛り上がらない方が都合が良い。約20%~25%程度の固定支持層・動員力を有するともいわれる彼らにとり、投票率が低い方が、強硬派の候補者が当選する可能性が高まるからである。
しかし、それでは困る人物がいる。ハメネイ最高指導者だ。ハメネイ師を頂点とする体制指導層にとり、「イスラム革命体制の護持」が最優先事項であり、大統領選挙での投票率が、革命体制への国民の支持、国家の団結を示すバロメーターと認識されているからである。だからこそ、ハメネイ師は、国民に対して常に積極的な選挙への参加を呼びかけ、それにより諸外国に対してイランの力を誇示できると繰り返し発言しているのである。
だが、そこにはジレンマがある。自身も強硬派であるハメネイ師にとり、広範な国民の参加を得た大統領選挙を実施する必要がある一方で、それは、自らの選好する候補者ではない大統領が誕生してしまう危険性をはらむものとなる。
しかし、40年以上続くイスラム革命体制には、それを解消する仕掛けが組み込まれている。「憲法擁護評議会(GC:Guardian Council)」である。
イランの大統領選挙には、「記念出馬」も含め、時に1、000名以上もの立候補者が出る(前回(2017年)は、1、636名が候補者登録した)。しかし、憲法擁護評議会が最高指導者の意向を汲み取って事前審査でふるいにかけ、大統領候補は数名(過去の例では2名~10名程度)にまで絞り込まれる。このようなスクリーニング・プロセスを経るため、その中であれば誰が大統領になっても問題ない候補が既に選ばれているとも言える。これが諸外国から「正当な選挙ではない」と批判されるゆえんである。

しかし、国民的な人気のある立候補者の排除や、あまりにも偏った選定は、国民のしらけムードを助長し、政治離れを確定的にしてしまう。昨年2月の国会選挙では、現職議員を含め改革派・穏健派系の立候補者を大量に資格審査で落とした結果、革命後の国政選挙で過去最低の投票率(42.6%。テヘランでは約25%(注3))に沈んだ。憲法上、最高指導者に次ぐポストである大統領を選ぶ選挙で、この轍を踏みたくはないだろう。
(注3:過去12回実施された大統領選挙の平均投票率は約67%。ハタミ大統領が登場した1997年以降(6回)では、平均約73%に上る。なお、イラン政府発表の数字の信頼性の問題はあるも、過去120年間で最高を記録したとされる2020年の米大統領選挙における投票率は約66%であった。)
イラン人は熱しやすく、そして、イランの選挙は熱い。
「制限選挙」とのそしりを受けようとも、憲法擁護評議会の選別を生き抜いた候補者たちの戦いは真剣だ。「文明間の対話」を唱えたハタミ大統領(改革派)、国際的な孤立を招いたアフマディネジャド大統領(強硬派)、歴史的なイラン核合意(JCPOA)を結んだロウハニ大統領(穏健派)と、国の向かう方向性に大きな影響を与えうる大統領に誰を選ぶかは、一般国民にとっても重大事である。
人々は、サッカーの国際試合に勝った時のように通りに繰り出し、花火や爆竹、車のクラクションを鳴らしてのお祭り騒ぎとなる。候補者は地方遊説に出かけ、キャンペーン終盤戦には巨大なサッカースタジアムなどを貸し切り、大集会を催す。そこでは、支持者たちが、候補者のイメージカラー(かつてのムサヴィ候補は「緑」、ロウハニ候補は「紫」など)で統一したスカーフやTシャツを身にまとい、候補者の顔写真や旗を掲げ、政治的な意味の込められた歌や詩、スローガンを大合唱し、強烈な熱気に包まれる。かつてイスラム革命(1979年2月)を成就させたイラン国民の底力の片鱗を感じさせる。

しかし、このような盛り上がりが、今年は見られない可能性がある。
(参考:イランの大統領選挙については、拙稿「抵抗か協調か、イランの民意を左右する米大統領選(JBpress)」も参照ください。)
コロナ第4波
イランは、昨年2月以降、世界でもいち早くコロナ禍に見舞われた。今年4月に入り、家族・親族が集まるイラン正月(ノウルーズ、3月20日頃)の余波を受け、1日あたりの新規感染者数が25、000人を超え、死者数は約500人に迫るなど、感染状況は過去最悪となる「第4波」のただ中(注4)にあり、感染状況の酷い都市間の移動や夜間の外出の禁止、医療品や食料品店を除くほとんどのお店が閉鎖されるなどの制限措置が続いている。
(注4:1日あたりの新規感染者数25、582人(4月14日)、死者496名(4月26日)は過去最悪の数字。)
このようなか、今年の大統領選挙ではいかなる物理的な集会の禁止が発表されており、「候補者は、公式なメディアの潜在能力とインターネット空間を活用できる」とされている。
国家が握るメディア
「すべてのマス・メディアは国家の人民の教育者である。ゆえにマス・メディアは全人民を教育する義務がある。」(イマームホメイニ金言集)
これは、イスラム革命を主導した故ホメイニ最高指導者の言葉である。そして、革命成就と同時に、ホメイニ師支持勢力がイラン国営ラジオ・テレビ公社(NIRT)を手中に収め、それ以降、イラン国営通信(IRIB:The Islamic Republic of Iran Broadcasting)として維持・運営されてきている。
イランでは、民間放送が一切認められていないため、国営放送の重要性は際立っており、それは憲法の規定からも明らかである。イラン・イスラム共和国憲法では、国営放送についてわざわざひとつの章(第12章)を割き、国営放送総裁の任命や罷免は最高指導者の専権事項と規定している(第175条)。国民の識字率が低かった革命当時から、広大な国土の隅々にまでリーチできる放送局は、極めて大きな影響力を有していた。
当然のことながら、大統領選挙における国営放送の影響力も無視できないものがある(注5)。4月13日、国営放送幹部は、計900時間もの特別選挙番組を用意していると述べている。24時間ぶっ続けでも1か月以上の長さに及ぶものであり、国営放送の全チャンネル(50以上の国内・地域TVチャンネルがある)、中東地域向けのアラビア語海外放送(al-Alam)、外国人向けの英語放送(Press TV)などを含めるとしても、相当な熱の入れようである。
(注5:米国のメリーランド大学がカナダ・トロントに本拠地を置く世論調査会社「Iran Poll」と共同で実施した今年2月の世論調査では、回答したイラン人の実に75%が国営放送を「大いに」又は「ある程度」国内外のニュースを得るために利用しているとの結果が出ている(インターネットは65%、ソーシャル・メディアは63%)。)

大統領候補たちの「バトルロイヤル」
大統領選挙で筆者が最も楽しみにしているのが、この国営放送による選挙特番のハイライトとなるであろう、大統領候補全員によるテレビ討論会である。短い選挙期間中に3回実施され、テレビとラジオで全国に生放送される。
この討論会では、国営放送局のスタジオに候補者全員が一堂に会し、国政にかかる様々な質問についてそれぞれの見解を表明し、それに対しての意見や反論をぶつけ合う。しかし、時に議論が白熱し、ヒートアップした候補者同士が激しく「口撃」し合い、レフリーたる司会者の制止を振り切って、個人攻撃や暴露合戦などの「場外乱闘」につながることもある。体面を重んずる国イランでの大統領候補同士による直接的な非難合戦は国民の興味・関心を惹起する。選挙の流れを一気に変える可能性を秘めた名物・爆弾企画である。
前回選挙では、再選を目指すロウハニ大統領とジャハンギリ第一副大統領の現職タッグに対し、3度目の正直を狙うガリバフ候補が果敢に挑むも返り討ちに合い、一方でメインイベンターと目されたライシ候補が存在感を示せない結果となり、最終的な選挙結果に大きな影響を与えたとされる(注6)。
(注6:ロウハニ大統領が再選を果たし、ガリバフ候補は投票日直前に撤退。ライシ候補は次点に終わった。)
「雄弁」を美徳とするイラン人にとり、ディベート能力の高さは大統領にとり極めて重要な資質と認識されている。中世イランの大詩人サアディーは「雄弁の達人」として愛されており、冒頭の女性スパイも「イラン人に好かれるためにはサアディーをもっと勉強せよ」とイラン潜入前に指導を受けている。イラン人は、巧みな話術で自らの主張を力強く発信する人物を好む。「男は黙って・・・」という訳にはいかない。ペルシャ語の大家:岡田恵美子先生は、その著書『言葉の国 イランと私』の副題に「世界一お喋り上手な人たち」と添えている。
そして、これは筆者の個人的な考えだが、候補者の「声質」も実は重要な要素ではないかと思っている。最近では「イケボ(イケメンボイス)」と呼ぶのだろうか。興奮して早口となり、かすれたり、甲高い声でまくし立てるのはイケてなく、やはり、やや低音で重みと響きのある声でよどみなく弁舌を振るう者が有利な気がしている(注7)。ペルシャ語を解さない読者の方々も、YouTubeなどで、ザリーフ外相やロウハニ大統領、ハタミ元大統領、ハメネイ最高指導者などの演説を一度聴いてみてほしい。
(注7:低い声が政治家の好感度を上げるという研究結果は多くあり、英国のサッチャー元首相がボイストレーニングを積んであえて声を低くした逸話は有名である。)
国営放送とロウハニ政権の熾烈な戦い
ポスト・ロウハニを睨んだメディア上での戦いは、何年も前から既に始まっていたが、ここ最近さらに激化してきている。冒頭で紹介した国営放送によるスパイ・ドラマ『Gando(ガンドォ)』はその一例である。
Gandoシリーズ1は、米国が核合意から一方的に離脱したことに対抗し、イランが徐々にその核開発活動を拡大し始めたタイミング(2019年5月)に合わせるかのように放映が開始(同年6月8日)され、瞬く間に人気を博す。そして、シリーズ2は、今年3月20日以降、コロナ禍のノウルーズ(イラン正月)休みのゴールデンタイムに毎晩放映された。
このシリーズは、革命防衛隊傘下の企業が制作したとされ、その内容は、シリーズ1は米国中央情報局:CIA、シリーズ2は英国秘密情報部:MI6のスパイの暗躍に対して、最新機器を駆使して対抗し、昼夜を惜しまず「敵」の陰謀を挫こうとする革命防衛隊の諜報部隊の献身と活躍を描いたものである。シリーズを通じて、西側諸国、とりわけ英・米、さらにはイスラエルが徹底的に悪者扱いされ、ロウハニ政権、とりわけザリーフ外相率いる核交渉チームを、敵の浸透に脆弱な者たちとして極めて批判的に描かれている。
毎回冒頭で「このシリーズは、実話に基づいて作成されたものである」との説明が付され、物語には、実際にイランでスパイ容疑として逮捕・拘束されたジャーナリストや外交官に酷似した人物が登場する。
もともとイランには「陰謀論」に傾きがちな国民性がある。それは、実際にCIAとMI6の共謀によって国民的な人気を博したモサデグ政権が転覆(1953年8月)された記憶によるものかもしれない。また、昨今のイラン人科学者の暗殺や核施設における不可解な爆発事件など、ドラマの話を地でいくような事案が国内で相次いでおり、一部の視聴者には、リアルな世界でも続いているかのように感じられたのかもしれない。
そして、ウィーンでの核合意再生に向けた米・イラン間の「間接協議」が開始される直前、唐突にこのシリーズの放映が中止(4月2日)された。普段は「国営放送なんかを観ているのは、ネットがない田舎の貧乏人くらいだ」と軽口を叩いている筆者の周りのテヘラン子も、「このシリーズだけは特別だ」と言い、父子が毎晩かぶりつきで観ていた家庭もあり、突然の放映中止を嘆いていた。
このシリーズについては、昨年、ザリーフ外相がハメネイ最高指導者に書簡を送って抗議したとされ、今回の放映終了も、ロウハニ政権からの圧力があったとの報道もあるが、真相は定かではない。当地の保守系メディアは、「Gandoシリーズ3はウィーンで?」と皮肉った見出しを掲載した。
そうこうしているうちに、「Gando3の舞台」とされたウィーンで、国営放送と核交渉チームの空中戦が表面化した。イランの核交渉チームを率いて現地入りしていたアラグチ外務次官(元駐日大使)は、4月20日、「Press TVの“informed source” (消息筋・情報通)が誰だかは知らないが、明らかに情報に通じていない(not “informed”)」とツイートした。この真意については色々と取り沙汰されているが、核交渉チームは、一方でハメネイ最高指導者の示した交渉のレッドラインに従いつつ、他方で、核合意関係国(英・仏・独・ロシア・中国)等、そして間接的に米国との間でデリケートな交渉を進めている中で、Press TV(イラン国営放送の英語放送)が、その努力を背後から撃つような報道を続けたことに、堪忍袋の緒が切れたようであった(注8)。
(注8:核交渉チームは、最高指導者から示された「イランは交渉を急いではいないが、時間を消耗するような交渉も行わない。米国とは直接交渉しない。米国が制裁を解除し、それをイランが検証した後に、イランも核合意上のコミットメントに復帰する」などのラインと齟齬がないようにウィーンにて交渉を続けているが、イラン国営通信の一部であるPress TVが、「消息筋・情報通」が述べたとして、そのラインに反するような交渉が行われているかのような報道を流していた。)
GAME OVER
同じ4月20日の深夜、筆者の携帯に、「国営放送のチャンネル3を観てみろ。ペルセポリス(注:イランの人気サッカークラブ)の勝利だ!」と、試合終了寸前のスコアボードの写メが添付されたWhatsAppメッセージが入った。旧知のイラン人ジャーナリストからの唐突な連絡。これまでサッカーの話題など交わしたこともないのに、と不思議に思いつつもチャンネルを合わせた。
ACLアジアサッカー・チャンピオンズリーグで、イランのペルセポリスFCがインドのゴアに逆転勝ちを決めた試合の放送であった。しかし、彼の真意はその先だったようだ。サッカー中継が終わると直ぐに、「Payan-e Bazi」(パート1)と題された20分程度の”ドキュメンタリー”番組が流れた。
この番組では、米国のマレー・イラン担当特使と国際危機グループ(ICG)に焦点を当て、イラン核合意は、ICGが15か月も前に準備していたもので、ザリーフ外相率いるイランの核交渉チームに「押し付けられた」ものだと主張。2015年当時、核合意に喜びを爆発させ、街に繰り出して浮かれ踊るイラン国民の映像を繰り返し流しつつ、米国は、今再び、事前に用意された計画をイランに押し付け、制裁を「紙の上」でのみ解除しようとしていると警告を発している。
放送のタイミングも絶妙だった。ウィーンでの核合意再生に向けた交渉が進む最中であったことに加え、普段は国営放送を観ない層も、国民的な人気スポーツであるサッカー中継は例外的に観ていた。「罠にはめられた!」とは、筆者と同様に、サッカー中継の流れからそのまま”ドキュメンタリー”番組を観てしまった友人の言葉だ。「Payan-e Bazi」とは、「試合終了・終局」、つまり、「西側との茶番、核合意のお遊びは終わりだ」という皮肉なのであろう。

4月22日、イラン外務省は「外務省及び核交渉チームに対するメディア攻撃の激化」に対する声明を発出し、上記の事案(「Gando」、「Payan-e Bazi」、Press TVの報道等)などに言及した上で反論を展開し、「過去数年間、忍耐と沈黙を守って職務を遂行することに専念していたが、国益を守るため、破壊的な勢力に対して警告を与える必要がある」と異例の強いメッセージを発出している。
インターネット、ソーシャル・メディアの役割(次稿に続きます)
今回の拙稿では、イランの大統領選挙に向けた既存のマス・メディア、国営放送とロウハニ現政権の戦いについて紹介した。
次回の寄稿では、ザリーフ外相の突然のClubhouse乱入(3月31日)や、流出した同外相の内部記録用音声のClubhouseでの配信(4月24日)などにも触れつつ、インターネットやソーシャル・メディアの役割、イランにおけるTwitter、Facebook、Instagram、 Telegram、WhatsAppなどのプラットフォームの現状とそれに対するイラン体制による規制などについて少し掘り下げてみたい。
(寄稿:角 潤一(在イラン日本国大使館 一等書記官)、編集・デザイン:深山 周作)