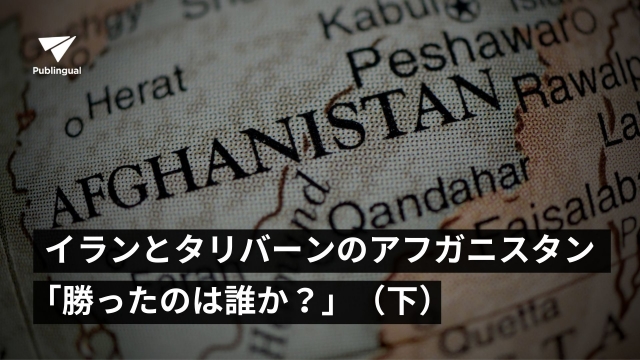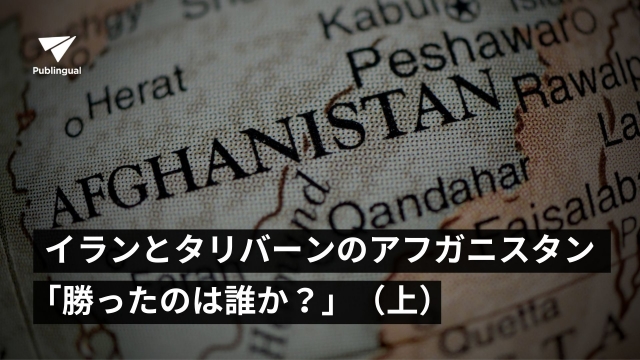「もし、あなたがイランの最高指導者だったら、どうするだろうか?」
時に相手の立場に立って想像することは、外交のみならず、ビジネスでも恋愛でも有用な手段であろう。筆者は、かつて都内某所でのあるシミュレーションで、24時間、最高指導者を演じたことがある。
当時とは多少状況が異なるが、どう見積もってもイランの置かれた立場は厳しさを増している。では、この1年どうだったのか、イラン側の立場、ハメネイ師の視点で考えてみたい。
対米関係:「最大限の圧力」VS「戦略的忍耐」
米国の「最大限の圧力」に対し、イランは「戦略的忍耐」を徹底し、トランプ退場を待つ姿勢を貫いた。
「バイデンでも誰でもいい。とにかく、トランプでなければ良いのだ。」
これは、米大統領選挙の雌雄が決する前、筆者と長年付き合いのある、ベテランのイラン政府関係者の言葉だ。彼は「トランプ大統領は全く信頼できず、予測不可能。我々の(対米関係マネージに向けた)努力を台無しにしてきた。」と憤慨して続けた。
昨年1月3日未明、イランのイスラム革命防衛隊(IRGC)コッズ部隊司令官ソレイマニは、訪問先のバグダッドで米軍のドローン攻撃を受け、乗っていた車両は大破、ばらばらになった肉片の中に、司令官が愛用していた赤い指輪がはめられた指があった。
米国からすれば「テロリストの親玉を殺った」ということなのであろうが、イラン側からみれば、革命の精神を体現し、過激派組織「イスラム国(IS)」などの外敵から国を守ってきた「英雄の完璧な殉教」なのである。

寵愛していたソレイマニの死に、最高指導者が大泣きする姿が国営放送で報じられ、「激しい報復」が宣言された。5日後(8日未明)、イランは駐イラク米軍基地に弾道ミサイル十数発を打ち込んだ。
昨年の今頃、「米・イラン全面戦争か?」ともいわれ、邦人退避に奔走した日々を思い出すとぞっとする(※参考.「外交」(都市出版))。20年以上イランを見てきた筆者自身、元来現実主義的なイランの判断に期待しつつも、何らかの予期せぬ突発事故が起きるのではないかと懸念していた(実際のところ、今も常に心配している)。
米国による矢継ぎ早の圧力政策(度重なる制裁の強化、原子力空母ニミッツや戦略爆撃機B52のペルシャ湾への派遣等)を前に、イランの「戦略的忍耐」は、手も足も出せない「無策の状態」だったと見ることもできるかもしれない。
しかし、ハメネイ師を中心とするイラン指導層の至上命題は「イスラム革命体制の護持」。策を弄することで体制崩壊の危機を招き得るのであれば、じっと耐えるのが国益を守る上で得策であろう。
その結論に至るまでには、イランの体制内で真剣な検討が行われたことは確実である。
西方:イラク、シリア戦線
イランの安全保障上、極めて重要な西方、イラク・シリア方面に目を向けてみよう。イラン・イラク戦争(1980年~88年)の記憶がまだ人々の頭から消え去っていないため、この戦線を抑えることは国民の支持を得る上でも重要である。バグダッドの大使館に2年間(2010年~2012年)勤務した筆者も、現地で「イランの影響力」云々という話を日々耳にした。
しかし、軍師ソレイマニ亡き後、イランは「押し込まれている」。イラクでは、昨年5月、親米派ともいわれるムスタファ・カディミ前国家情報機関トップがイラク新首相に就任、シリアではイランがこれまでに築いた拠点をイスラエルに次々と爆撃されている。
ハメネイ師がソレイマニの後任として司令官に任命したカーニは、あまり目立った動きを見せていない。それはカリスマ性のあった前任者の動きがそもそも例外的であり、対外工作部隊として通常のオペレーションに戻ったということかもしれないし、体制で一致した「戦略的忍耐」政策に従っているということなのかもしれない。
カーニ司令官は、影響下にあるイラクの民兵組織に対して米軍への攻撃を控えるように指示した(2020年11月頃)ともいわれている。
1月20日、世界がバイデン政権誕生に沸き立つ中、翌21日、バグダッド市内の市場で連続自爆テロが発生、死傷者140名以上の大惨事となった。IS掃討後、自爆テロが激減していたイラクにおいて、これは2018年1月以来の大規模テロであり、ISが犯行声明を発表した。

イランは隣国でISが勢いを盛り返すことに危機感を高めつつ、IS掃討の功労者たるソレイマニ司令官を排除した米国に対して、「それ見たことか」という想いであろう。
南方:湾岸諸国とイスラエルの接近
視点をペルシャ湾の向こう側、湾岸諸国へ移してみよう。
筆者の論考に「湾岸諸国との関係が抜け落ちている」と指摘を受けることがあるが、正直に言えば、それが(筆者の感じる)イランの実感を反映しているという側面がある。
体制の生き残りを目指すイランにとって、最大の関心事項はやはり米国の動向であり、対岸側が騒ぐほど、イランはサウジアラビアを含む湾岸諸国が脅威になるとは感じていない。
トランプ政権末期、イスラエルはアラブ首長国連邦(UAE)、バーレーン、さらにはスーダン、モロッコといったアラブ諸国との外交関係樹立を次々に発表した。
昨年夏のイラン国内での核施設の不審な「爆発事故」や11月末のイラン核科学者モフセン・ファクリザデ氏の暗殺など、イスラエルの関与が疑われる事案が相次いでおり、イランとして神経をとがらせているのは間違いない。
しかし、同時に、イスラエルによってイランの生存権が明日にも奪われるというほどの脅威も感じていない。
イランにとり、イスラエルの存在が、目と鼻の先の湾岸諸国に公然と出現したことは面白くはないだろうが、リスクを冒して何らかの報復をするほどではないとの判断が働いているようだ。
「これまで水面下であった湾岸でのイスラエルの動きが表に出てきただけ」との冷めた見方をとりあえずは示している。
こうした状況について、あるイラン人ジャーナリストは、「米国の対イラン政策が肝。その他の国々は所詮は(米国の政策を反映せざるを得ない)「判子」のようなもの。オバマ政権下のイラン核合意(JCPOA)も、サウジアラビアやイスラエルの反対があっても実現した。米国の同意なくして、イランへの単独攻撃もできないだろう」と楽観している。
しかし、ビジネスしかり、恋愛しかりであるが、「認識のギャップ」には常に注意しなければならない。とりわけ、イスラエルについては、同国を知る多くの先達によれば、自国の安全保障を脅かすものに対しては、「極端かつ徹底的にやる」のだそうだ。
確かに、その成り立ちの歴史からも、また狭い国土に近接するレバノンやシリアにまでイランが迫ってきていることを踏まえてイスラエル側の視点に立てば、存亡に直結する脅威であり、徹底的にその芽を摘んでおきたいと考えるのは普通のことなのかもしれない。
この原稿を執筆しているさなかの1月26日、イスラエル国防軍参謀総長は、テレビで声明を発表し、「イラン攻撃計画の準備」を進めるよう軍に下命したことを明らかにした。バイデン政権が安易に核合意へ復帰しないよう牽制する意味合いがあるといわれている。ただし、これもイラン目線からすると、イスラエルが表だって威勢の良いことを言うときはハッタリで、本気でやるときは静かにやってきて、実行後も否定も肯定もしないものだと捉えている。
※注.東方(とりわけ中国)との関係については、拙稿「Wedge Report:米大統領選を前に中国と〝急接近〟するイランの真意」を参照下さい。
イランの国内情勢:経済制裁、コロナへの対応
国の指導者たるもの、外交のみならず、当然国内の情勢に目を向けなければならない。イスラム革命(1979年)から40年以上、国民の過半数が革命を知らない世代となるなか、革命の理念と体制への支持を維持していくことは容易ではない。
まずは国民のおなかを満たすことが最重要課題である。イランの最高指導者は、毎年、イラン正月(ノウルーズ。3月21日頃)に、その年のスローガンを発表している。昨年3月から掲げられているのは「(国内の)生産の飛躍」であり、持論の「抵抗経済」、つまり、外国に頼ることなく、自国の能力を活性化させることで、この苦境を乗り切ろうというものだ。
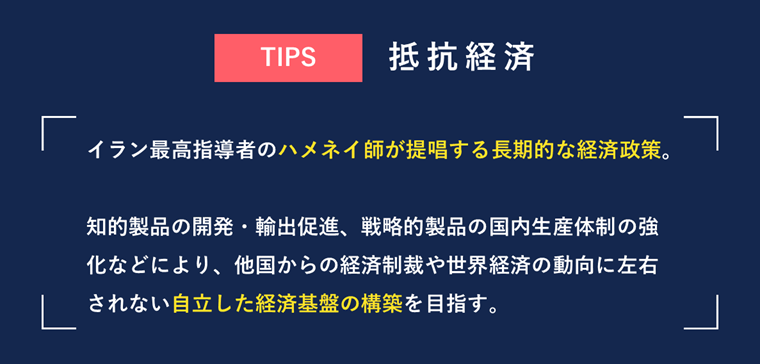
8,000万人以上の中東地域有数の人口を抱え、自国内だけでもある程度独立したマーケットとして機能していること、一定の工業技術力と食料自給率を有していることなどから、イラン経済のレジリエンス(強靱性)は我々の想像を超えるものがある(※参考.Battered by U.S. Sanctions, Iran Finds a Lifeline in Domestic Economy(THE WALL STREET JOURNAL))。
筆者の身近な例を挙げれば、制裁の影響か、スタバなどの外国製エスプレッソ・カプセルがスーパーから姿を消すも、すぐにMade in Iranの類似品が(味はともかくとして)より安価に出回っている。
しかし、根性論のスローガンだけでは腹はふくれない。如何に「制裁慣れ」し、辛抱強い国民にも限界がある。イラン政府は、全人口の約75%にあたる、6,000万人を貧困層と試算しており、これは貧富の差が大きく広がり、特にかつての中間層が貧困層へと吸収されつつある窮状を示している。
そのような状況に追い打ちをかけているのが、昨年2月から急速に拡大した新型コロナウイルスである。あまり認知されていないかもしれないが、コロナ累計感染者数が1万人を超えたのは(中国、イタリアに次いで)イランが世界3番目であり、日本の公館所在地で(武漢と同じ)感染症危険レベル3となったのは、テヘランが最初だった。
かつては、「制裁は効いていない」とその効果を認めたがらなかったイラン政府も、今やその影響により国民生活が逼迫していることを公言し、「経済戦争」(特にコロナ禍においては)「医療テロ」「人道に対する罪」だと米国を声高に非難する方向に舵を切っている。
昨年3月には、米国が強い影響力を有するIMFに対して、革命後、初めて緊急融資(コロナ対策のための50億ドル)を要請した。
イランは、海外にある自国の凍結資産を取り戻すことにも力を注いでいる。とりわけ、その資産規模の大きさ(70億ドルとされる)などから、ターゲットになっているのが韓国である。米国の対イラン制裁に伴い、韓国の銀行口座から送金できなくなったイランの資産であり、主に韓国がイランから輸入した原油などの代金とされる。
そんな中、ソレイマニの一周忌(1月3日)が静かに過ぎようとしていた1月4日、革命防衛隊が、韓国籍の石油タンカーをホルムズ海峡で拿捕したとのニュースが飛び込んできた。イラン側の発表によれば、「海洋環境保護に関する法律への度重なる違反」がその理由だ。
しかし、凍結資産と拿捕の関連性を疑う向きが多い(※注.イラン政府は否定している)。
緊張感を増す核問題交渉
さて、いよいよ本丸である核問題へと移ろう。
イランは、韓国籍タンカー拿捕と同じ1月4日、中部フォルドゥの核施設でウランの濃縮度を20%に引き上げる作業を開始したと発表した。2015年のイラン核合意成立前の水準に濃縮レベルが戻ることを意味する。
これを受け、「イランの核開発拡大に向けた強硬姿勢」「核合意修復はより困難に」といった見出しが日本を含むメディアの見出しを飾った。
果たしてイラン側の事情から見ればどうだろうか?
まず、イラン核合意から一方的に出て行ったのは米国である。核合意により核開発に一定の制限を加えることの見返りに得るはずであった経済的な果実は得られておらず、この点において欧州諸国はそのコミットメントを果たせていない。
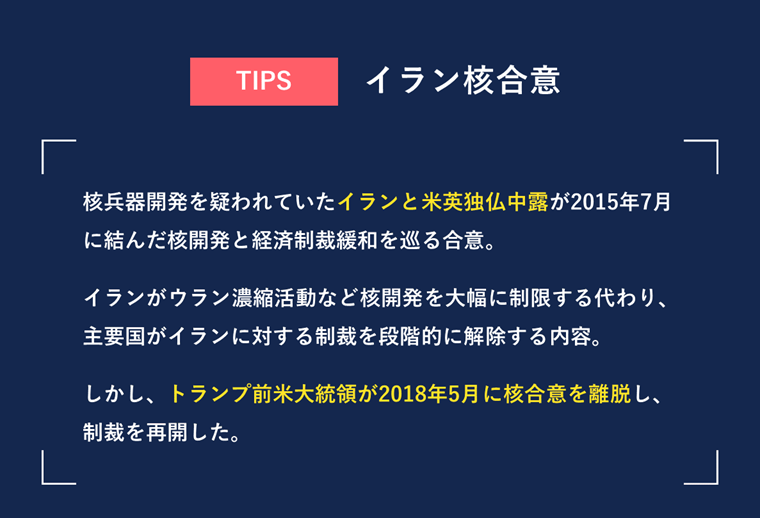
それでも、イランは約1年間にわたって自らのコミットメント(核活動の制限)を受け入れていた。しかし、2019年5月、米国がイラン産原油の全面禁輸に踏み切ったことを受け、徐々にそのコミットメントを逓減させる方針に転換した。
ただし、ソレイマニ暗殺直後となった昨年1月5日の逓減措置の最終段階の発表時にさえも、国際原子力機関(IAEA)との協力継続を宣言し、核合意から離脱はしなかった。
今回の20%ウラン濃縮の開始は、イラン国会で可決された法案に基づく行動である。事前にIAEAへの通報も行っている。
この法案も「核開発拡大法案」などと報じられることが多いが、実際には、直訳すれば「制裁解除及びイランの国益保護に向けた戦略的措置」法案(2020年12月2日可決)であり、その目的は明白である。
「米国が核合意に復帰するか否かは全く問題ではく、我々は全く急いでもいない。我々の要求は制裁解除である。」「核合意のコミットメント廃棄に関する国会と政府の決定は正しい。」とハメネイ最高指導者は、1月8日の演説で、核合意に対する姿勢を明確化した。
そして、最高指導者事務所HPに、11日以降、ザリーフ外相、ガリバフ国会議長、ラリジャニ最高指導者顧問、ジャリリ国家安全保障最高評議会(SNSC)最高指導者名代、サレヒ原子力庁長官など、かつての核交渉責任者や外相経験者による一連のインタビューを掲載し、イラン体制全体として、一枚岩となって制裁解除を追求していくことを示そうとしている。
バイデン大統領の就任直後の22日、「Foreign Affairs」に掲載された寄稿において、ザリーフ外相は、「イラン人の(戦略的)忍耐も切れつつある。バイデン政権にとっての機会の窓が永久に開いているわけではない。ボールは明らかにワシントン側にある」と改めて強調している。
ここまで見てくると、イラン側の意図は極めて分かり易いのではないか。ウラン濃縮20%という札を切り、体制全体で意思統一を図り、それを明確に発信している。もっとも「米国の核合意復帰に固執しない、急いでもいない」というのはイラン流の交渉術だろう。そもそも、米国が動かなければ、制裁は解除されないのだから。
しかし、ペルシャ絨毯屋で、いきなり手に入れたい絨毯の値段を聞くほど野暮なものはない。
バイデン政権の最優先事項は「コロナ・経済・人種・気候」の4分野とされ、就任直後に発表された施策も、およそそれに沿ったものになっている。イランとしては、無策でいるわけにはいかず、欧州諸国に核合意でのコミットメントの履行を求め、米国に対しては「新政権が核合意へ早期に取り組むよう仕向けたい」ということではないか。
イランの核開発の拡大やペルシャ湾における緊張を高めるような動きは、米大使館占拠事件(1979年)以降、米国内にいまだ渦巻く根強い反イラン感情を刺激し、またサウジアラビアやイスラエルなどが唱える「イラン脅威論」を裏付け、バイデン政権の身動きをとれなくさせる危険性もはらむ「諸刃の剣」。
国外からの圧力が強まれば、イラン国内の強硬路線が勢いづき、「対立の負のスパイラル」に陥りかねない。
今年6月18日に大統領選挙を控えるイラン。そこに至るまでの米国との攻防が、8年ぶりの大統領の交代(※注)にどのような影響を与え、核問題や米イラン関係が今後どのように進んでいくのか、注目していただきたい。
※注.イランの大統領は、米国と同様に1期4年間の連続2期までであり、現在2期目のロウハニ大統領(穏健保守派)は出馬できない。
(寄稿:角 潤一(在イラン日本国大使館 一等書記官)、編集・デザイン:深山 周作)