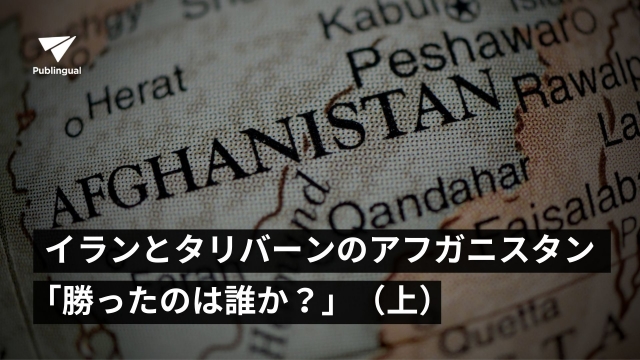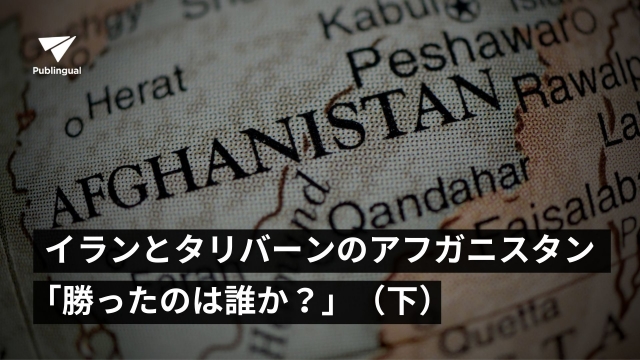この記事の目次
※本稿は、個人的な見解を表明したものであり、筆者の所属する組織の見解を示すものではありません。また、固有名詞のカタカナ表記は一般的な表記に合わせています。
『AGHA’ZADEH』
うら若いイラン人女性がメルセデスベンツに閉じ込められ、断末魔の叫びとともに車体ごとスクラップにされ、四角い鉄の塊となった残骸から鮮血がしたたる、という強烈なオープニング。筆者の中では、『進撃の巨人』第一話以来の衝撃だった。
これは、イラン版ネットフリックス「Namava」で大ヒットしたドラマシリーズ『AGHA’ZADEH(アーガーザーデ)』の第一話冒頭シーンである。コロナ禍のセミ・ロックダウン下、イラン人も、我々と同様、閉じ込められた自宅で持て余した時間を埋めるように、ネット・ストリーミングで映画やドラマの世界へ没入した。

このドラマでは、「アーガーザーデ」(注1)と呼ばれる権力者の子息たちが、ドバイへはプライベートジェットで飛び、テヘランでは現代美術品のオークションに参加、高級ブランドを身にまとった女性たちが、ビリー・アイリッシュの”bad guy”をバックグランドに踊り、禁酒国イランでは御法度の“特殊飲料”が大量消費されるパーティーなど、イラン社会のタブーを謳歌する姿が映し出される。しかし、このドラマの最大のテーマは、「経済腐敗・汚職との闘い」であり、「アーガーザーデ」やその背後の黒幕たち(政府高官・閣僚など)の腐敗・不正に立ち向かう司法機関の活躍を描いている。
(注1:“Aghazadeh”という言葉はもともと、個人資産が10億ドルを超える「大富豪のムッラー」として『フォーブス』誌に取り上げられたこともある故ラフサンジャニ師(元大統領)の子息たちをターゲットにした造語。和訳すれば、“親の七光り”、“二世”、“ぼんぼん”といったところだが、より侮蔑的な響きが感じられる。)
たしかに、大学を出たばかりのような若者たちが平日の昼間から高級レストランでたむろし、見たこともないようなスーパーカーで爆音を轟かせて乗り回しているのを目にすることがある。そして、そのような「アーガーザーデ」たちの振る舞いに、人々は、羨望や嫉妬、侮蔑の入り交じった視線を向けている。
経済腐敗・汚職の撲滅や国内の経済的ミスマネージメントの是正は、核合意による経済制裁解除と並ぶ、イラン大統領選挙の大きな論点の一つである。このドラマシリーズも前稿で紹介した『Gando』同様、革命防衛隊(強硬派)傘下の企業が制作したとされ、このシリーズが、司法権(強硬派)のイメージアップに一役買っていることは事実であろう。
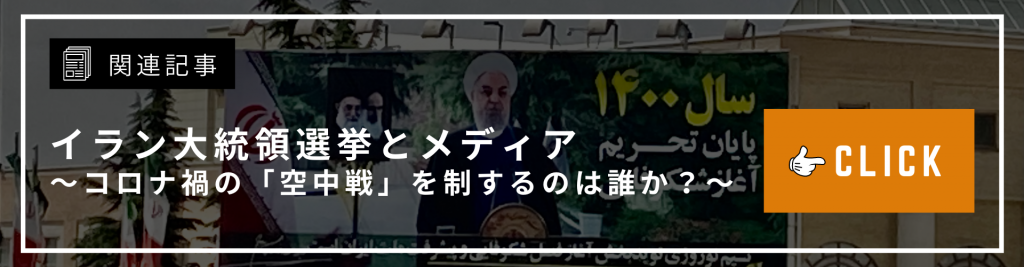
前稿に続き、冒頭にてコロナ禍でヒットしたドラマシリーズを紹介したが、この伏線の意図については、拙稿の末尾を御覧いただきたい。以前、旧知の政府関係者が、「ドラマや映画はその時々の世相・時流を反映している。イラン社会を理解したければ、睡眠を削ってでもフォローすべきだ」と助言してくれたのを、今更ながらに思い出している。
前稿では、イランの大統領選挙の仕組みを紹介し、既存のマス・メディア、とりわけイラン国営放送(IRIB。強硬派)とロウハニ現政権(穏健派)との戦いを取り上げた。
本稿では、TwitterをはじめとするSNSが民衆の大きなうねりを生んだ2009年の大統領選挙から最近の「Clubhouseの登場」など、イランにおけるネット空間やソーシャル・メディアの役割、そしてそれが大統領選挙に与える影響について少し掘り下げてみたい。
そもそも繋がっていたい人々:イラン人
ある国の国民性を一般化するのは難しい。それでもイランの人たちは、一般に、人懐っこく、寂しがり屋で、パーティー好き、お客をもてなすことを大切にし、家族や恋人はもとより、単なる友人知人ともつながっていたい「濃厚接触民族」だと言えるだろう。
「Che khabar? Delam tang shod」(どうしてる?会えなくて寂しい(直訳すると“心臓が縮んでしまった”))と、同性異性にかかわらず、先日会ったばかりなのに毎日のようにメッセージを送ってきたりする。
イラン社会も、ガッツリ徒党を組むわけではないが、バザール商や宗教界、軍関係者(革命防衛隊・国軍)、地域の部族社会など、ゆるゆるとした無数のネットワークから構成されているといわれる。イランの体制の意思決定も、頂点に立つ最高指導者の「鶴の一声」だけで決まるのではなく、複数のネットワークの力のバランス関係から生み出されると表現されることがある。
このような緩やかなネットワークも、一度何らかの「刺激」を受け、熱を帯びると、シナプスにように一気に繋がって「核融合」し、爆発的なエネルギーを生むことがある。1979年のイスラム革命や2009年の大統領選挙後の「グリーンムーブメント(緑の運動)」(後述)なども、その一例と言えるかもしれない。
昨年までイランにいらした山岸智子先生は、編著『現代イランと社会と政治』の副題に「つながる人びとと国家の挑戦」を添え、最終章に「ネットワーキング ― 領土を越えるイラン人意識」を執筆されている。
ネット空間上の「ペルシャ帝国」
20年以上前、筆者が外務省に入省した際、いわゆる「特殊語」としてのペルシャ語を専門語学として指定された。しかし、ネット空間では事情が異なるようだ。最近のある調査によると、筆者を含むペルシャ語話者の世界の総人口に占める割合はたったの0.7%であるのに対し、インターネット上で使用される言語としては第5位(3.0%)を占めるのだそうだ(注2)。
浸透するインターネット
順を追ってみていこう。
筆者が初めてイランに足を踏み入れた2000年当時のネット人口はたったの25万人。それが、2007年には1800万人に達し、当時の「中東地域」(注2)におけるネット人口の半分以上(53.7%)を占めていたとの統計がある。
(注2:冒頭のイラン版ネットフリックス「Namava」やイラン版YouTube「Aparat」、独自の検索エンジンなど、長年の制裁の功罪か、イラン独自のネット圏を構築している。ただし、この統計「Internet World Status」が対象とする「中東地域」には、ネット上のもう一つの大国である「オスマン帝国」つまり、トルコが含まれていないことには留意が必要。)
【2003年から2008年頃】 「Weblogistan」の登場
1997年、社会の変革と自由を求めるイラン国民の後押しを受け、地滑り的勝利によって誕生したハタミ政権(2期、2005年まで)。「文明間の対話」を提唱し、国際協調・国内改革路線を進もうとしたが、既得権益層(強硬派を含む幅広い保守派)の抵抗に遭い、国民の高い期待とは裏腹に、十分な成果を上げることができなかった。
改革の頓挫に落胆した人々は、より自由な自己表現の場を求めてネット空間へ「移住」し、自らのブログを次々と立ち上げていき、「Weblogistan(ウェブロギスターン)」(注3)などと呼ばれた。
(注3:「-stan」(~スターン)はペルシャ語で「~が多い場所」の意。)
【2009年】 Twitter革命:「アラブの春」に先駆けた「ペルシャの春」

Twitterで2009年に世界で最もつぶやかれた言葉は「イラン大統領選挙(#iranelection)」だった。
革命から30年の節目と重なったこの年の大統領選挙は、再選を目指す現職のアフマディネジャド大統領(強硬派)とムサビ元首相(改革派)の事実上の一騎打ち、闘いは少なくとも互角、選挙戦最終盤の盛り上がりから投票率が上がればムサビ候補有利との見方も強かった。しかし、蓋を開けてみれば、史上最高の投票率85.2%の下、アフマディネジャド大統領が得票率(62.63%)でムサビ候補(33.75%)に2倍近い差をつけての圧勝が発表される。
ムサビ元首相は、「多くの明らかな不正があり、敗北は受け入れられない」と主張。その主張は瞬く間に広範な社会運動となり、「私の票はどこへ?(Where Is My Vote?)」とプラカードを掲げた支持者たちが街に繰り出し、何か月にもわたり断続的に大規模な抗議デモを繰り返した。デモの情報はFacebook上などで告知され、それがTwitterやSMS(ショート・メッセージ・サービス)で共有・拡散された。さらに、抗議デモとそれを容赦なく弾圧する治安当局の様子がイラン市民により撮影され、YouTubeに投稿されると、抗議の熱はさらにヒートアップしてく。デモに参加していた26歳の女性ネダー(Neda Agha-Soltan)が銃弾に倒れ、鮮血にまみれ、目を見開いたまま絶命していく様は、未だに筆者の脳裏に焼き付いている。
最終的には、体制側によるインターネットや携帯電話などの遮断、徹底的なデモの封じ込めにより、ムサビ候補の選挙キャンペーンカラーから「グリーンムーブメント(緑の運動)」と呼ばれた民衆のうねりは鎮圧された。イランの人々の中には、この運動を指して、2011年以降の「アラブの春」よりも前に、「ペルシャの春」がやって来ようとしていたが、春を謳歌することはできなかったと悲しげに話してくれる人もいる。
SNSの興隆 vs 当局の規制の「トムとジェリー」
このようなイスラム体制を揺るがしかねないインターネットやSNSの影響力に対して、イランの体制指導層は警戒を強めている。ハメネイ最高指導者は、今年のノウルーズ(イラン正月。3月20日)の演説で「ネット空間をマネージする必要がある。現状は野放し状態だ」と指摘している。
2009年の「グリーンムーブメント」を受け、イラン当局は、Facebook、Twitter及びYouTubeを遮断した。

その後、当局は、2017年末から全土に広がった反政府デモを助長したとして、イランで圧倒的な人気を誇るチャットアプリ「テレグラム(Telegram)」を遮断する(2018年4月)。Telegramは、当時、総人口の半数以上の約4000万人超が利用するとされ、日常生活や商売の連絡に欠かせないインフラとなっていた。
この防衛策として国民の間に広がったのが、仮想プライベートネットワーク(VPN)という通信を暗号化して外国のサーバー経由で接続するアプリだ。VPNを介すことで、回線速度は落ちるが、当局に遮断されているウェブサイトの閲覧やFacebook、Twitter、YouTube、Telegramの利用が可能となる。
思い返してみると、たしかに、筆者がテヘランで研修していた2000年当時も、恐ろしく遅い電話回線のインターネットでなんとか辿り着こうとした海外サイトの多くは検閲され、ブロックされていた。しかし、どこからともなく、それを迂回するリンクが送られてきて、しばらくするとそのリンク先も当局に塞がれ、そうするとまた別の迂回リンクが回ってくるというイタチごっこだった。
また、この国の不可思議な一面であるが、イラン当局自身が遮断しているにもかかわらず、TwitterやTelegramなどを、多くの体制要人や国営の通信社などが活発に利用している。ハメネイ最高指導者は、ペルシャ語に加え、英・仏・独・西・伊・露・アラビア・トルコ・ウルドゥー・ヒンディーとざっと確認しただけでも10以上の言語でツイートしている(注4)し、ロウハニ大統領やザリーフ外相もそれぞれ約117万人(英語アカウント)、約167万人のフォロワーを抱えている。
(注4:現時点で、日本語はない。ハメネイ最高指導者のTwitter英語アカウントのフォロワー数は約89万人。5月15日現在。)
【「インスタグラム(Instagram)」~イランのインスタが熱い】
Facebookなどが遮断される中、画像や短い動画投稿が主体で特に若年層に人気の高いInstagramがイランのオンライン・コミュニティーで熱を帯びている。

2017年の数字であるが、イランはインスタグラムの利用者数が世界第7位。短い動画1本で1000ドルを稼ぐというセレブなインスタグラマーが誕生し、数百万のフォロワーを抱えるインフルエンサーも登場、多くの企業やホテル、レストランなどもアカウントを開設してビジネスを展開している。コロナ禍で顧客との対面販売ができなくなった若手アーティストなどは、インスタ上に「自らの作品の店」を構えて個人ビジネスを続けている。
イスラム教の戒律による締め付けが厳しい実生活から逃れて、当局の規制とギリギリのラインで自己表現を行う者、孤立しがちなマイノリティーらが居場所を求め、互いにつながりあって結びつきを強めている。社会のつながりが強まる一方で、その力を恐れて手綱を締める当局とのせめぎ合いも続いている(注5)。
(注5:Pharrell Williamsの「Happy」で踊る動画を投稿した若い男女や、屋上などでヘジャーブを脱いで自由を主張する画像を掲載した女性が逮捕されるなどの事案も続いている。一方で、ネット上の抗議運動が政府や司法を動かす事例(女性のスタジアムでのサッカー観戦の一部許可(2018年10月)やデモに参加した若者3名の死刑執行の一時停止(2020年7月)など)もごく一部ながら出てきている。)
Twitterと同じく、体制要人や政治家らも支持拡大に向けて積極的に活用している。約440万人のフォロワーを抱えるハメネイ最高指導者は、1投稿あたり平均36万「いいね(Like)」を獲得してインスタグラムのインフルエンサーのトップテン入りを果たしている。
筆者がセンター長を務める在イラン日本国大使館の広報文化センターも、ホームページやTelegram、Twitter(@japaniniran)のアカウントを活用しているが、やはり主戦場はInstagram(@japaniniran)である。
【「クラブハウス(Clubhouse)」の登場】

2020年3月に米国企業が開発した招待制音声SNS「Clubhouse」も徐々にイランに浸透し始めている。招待者数が限定されている希少性・特別感もあり、新しいもの好きのイラン人にはウケるようだ。政治家が一般市民と直接やりとりできることも、イランにおける新しい政治カルチャーとして注目されている。筆者も「入部」はしたものの、まだ「クラブ活動」は始めていないので、正直よく分かっていないのだが。。。
一方で、テヘラン子に聞いてみると、単なる「出会い系のアプリ」の一つとしか見なしていない向きも多いようだ。かつては、テヘラン北部のジョルダン通りなどの「ナンパ・スポット」へ高級車で乗りつけ、巨大スピーカーで西洋音楽をガンガンかけるのがモテる時代があった。しかし、男女の出会いもマッチング・アプリなどが流行り、コロナ禍のスマホ時代にはネット上の「空中戦」に様変わりしているそうである。
少々話題がそれたので、政治の話に戻そう。
最近、特に耳目を集めたのが、ザリーフ外相の「クラブハウス登場」(3月31日)であった。イラン政府関係者が開いた「部屋(room)」にザリーフ外相が入室すると、たちまちの「フルハウス」、8000人の定員に達した。そこで、ザリーフ外相は、自身が署名した(3月27日)25年間のイランと中国の包括的協力計画に対する説明や、(前稿で紹介した)自身がターゲットとなっていた『Gando』シリーズへの強烈な批判などを展開し、大きなニュースとなった。
ザリーフ外相のほかにも、ジャハンギリ第一副大統領、サレヒ副大統領兼原子力庁長官、ジョフロミ通信相など、大統領候補として期待を集めたロウハニ政権(穏健派)の政府高官らが次々とClubhouseに登場。Clubhouseが大統領候補たちの「停留所」になっているとも指摘された。
Clubhouseが話題を集めたもう一つの事例を見てみよう。
【ザリーフ外相の内部記録用音声の流出事件 ~ 「諸刃の剣」】
4月24日夜、Telegramにメッセージが入った。174.8MBのmp3ファイル。音声データにしてはかなり重い。
開いてみると、聞き覚えのある声(ペルシャ語)が聞こえてきた。ザリーフ外相の「イケボ」だ。

インタビュー形式のようで、長さをみると3時間11分もある。だが、彼(ザリーフ外相)とハメネイ最高指導者との特別な関係、国家安全保障最高評議会(SNSC)における意思決定の過程、昨年1月に誤って撃ち落とされたウクライナ航空機事件の裏側、アフマディネジャド大統領(当時)への辛辣な批判、イラン核合意(JCPOA)の成立を累次妨害しようとしたロシアの動きなどなど、たちまちその内容に引き込まれてしまった。
「Meidan hakeme!」
しかし、筆者の耳に一番残ったのは、この言葉だった。これは、直訳すれば「戦場が支配している(the battlefield rules)」の意であり、イラン・イスラム共和国においては、「外交」ではく、「軍事」が国の政策を決定しているとして、革命防衛隊、とりわけ昨年1月に「殉教」したソレイマニ司令官に対するフラストレーションを赤裸々に語ったものである。
これは、ロウハニ政権のオーラル・ヒストリー・プロジェクトとして、内部記録用に行ったインタビューの音声が外部に流出したもので、ロンドンに拠点を置く「イラン・インターナショナル」(注6)がClubhouseで同24日に配信、Telegramなどで瞬く間に拡散された。
(注6:サウジアラビア資本とされることから、保守的な筆者の悪友は「サウジ・インターナショナル」と揶揄しており、イランの現体制に批判的なペルシャ語放送局といわれる。)
この音声リークのニュースはイラン国内外で大騒ぎとなり、「あのインタビューを聞いたか?」と多くの友人知人らに聞かれた。皿洗いをしながら、湯船につかりながら、眠りにつくまでの枕元でと、筆者は通しで4回は聞いただろう。
Clubhouseを、自らの主張を表明する場としていち早く有効利用したザリーフ外相であったが、反対派からの攻撃手段としても使われる形となった。
大統領選挙へのインパクト
過去の大統領選挙、とりわけ前回2017年もネット上の選挙運動は活発だった。しかし、直近4年間でイランにおけるSNSユーザーは飛躍的に増大しており、そこに第4波の峠をようやく越したかに見えるコロナ禍が加わる。前稿で紹介したとおり、今年の大統領選挙ではあらゆる物理的な集会の禁止が発表されており、「候補者は、公式なメディアの潜在能力とインターネット空間を活用できる」とされ、地方遊説や大集会などの「地上戦」は封鎖されている。
最近の調査によれば、18歳以上の国民の73.6%がSNSユーザーであり、大統領選挙に投票できる有権者の大半をカバーしている。また、別の調査によれば、イラン国民8450万人のうち、インターネットアクセスを有するのは約70%の5916万人と割合的には4年前から横ばいであるが、Active Social Media Users数は、1700万人から2倍以上の3600万人に急増している。
大統領選挙におけるメディアの役割について、最近、イラン国営通信(IRNA)(注7)が興味深い連載を掲載している。メディア専門家らのWebinarの内容を報じたものだ。そこでは、Twitterや新たに登場したClubhouseがトレンド・セッターとなり、その情報をTelegramやInstagramが補完し、シェア・拡散、これを様々な既存メディアが報じることで完成すると分析している(注8)。
(注7:前稿で紹介したイラン国営放送(IRIB。強硬派)とは別組織。政府(文化イスラム指導省)傘下にあり、その時々の政権に影響を受けた報道傾向がある。なお、政治的な影響力の大きさでは、革命防衛隊系とされるFars通信やTasnim通信の影響力も注目に値する。)
(注8:イランで人気の高いSNSプラットフォームは、拙稿にたびたび登場するWhatsAppが第1位で、4770万人が利用しており、Telegram(4730万人)、Instagram(4400万人)と続く。Facebookは240万人、Twitterは200万人。)
まさにこれは先述のザリーフ外相の音声リーク事件に当てはまる。この事件は、Clubhouse × Telegramの連携で一挙に拡散、既存メディアで大きく報じられ、そのリークされた発言自体の重みも加わり、ザリーフ外相にとり「クリティカルヒット」となった。核合意の立役者であり、国民的人気の高かったザリーフ外相は、来る大統領選挙において改革派・穏健派の目玉候補であったが、それ故に、革命防衛隊などの強硬派から目の敵にされていた。ザリーフ外相は、自身のInstagramに大統領選挙不出馬の意向を表明(5月12日)し、外遊先のシリアへと旅立って行った。
もう一つ、このWebinarでは、今回の大統領選挙において、これまで以上に多くの根拠のない噂やファイクニュースが流れると予測し、正確な情報を報じるメディアの責務はより重くなると指摘している。
この点、最近、前代未聞の出来事があった。カナダに拠点を置くイラン人によるファクトチェック機関「FactNameh」の指摘を受け、ハメネイ最高指導者が自身の発言内容を訂正したのだ。問題となったのは、ハメネイ師がノウルーズの演説で、経済的な苦境にあるとされるイラン経済について、世界銀行の統計を引用し、「イランの経済規模は世界第18位である」と主張した点である。FactNamehは演説の中のそのほかの事項も含めて事実確認を行い、この点についてはどう見積もってもイランの経済規模はハメネイ師の主張よりも下位にあると結論づけ、「Nadorost(正しくない)」と判定した。ハメネイ師は、その後の別の演説の中で、「ある人たちが自分の発言の間違いを指摘してくれた。感謝したい」と述べ、自らの誤りを認めたのである。これは極めて些細ではあるが、興味深い出来事である。FactNamehは、大統領選挙期間中の候補者の討論会に対して、ライブ・ファクトチェックを行うとしている。
ハメネイ最高指導者は、5月2日の演説でも、大統領候補者に対して「裏付けのない公約はするな。計画を提示せよ」とポピュリズム的な傾向に走りがちな選挙キャンペーンを事前に諫める発言をしている。
「空中戦」観戦を
前稿から指摘しているとおり、強硬派は、国内唯一のTV・ラジオ放送局(イラン国営放送)を独占し、強力な通信社を擁している。近年では、豊富な資金力で、映画やドラマシリーズ、“ドキュメンタリー”を制作し、ロウハニ現政権を攻撃する一方で、革命防衛隊や司法権などのイメージアップを図ってきている。
5月15日18時、大統領選挙の立候補登録が締め切られた。
強硬派の期待を集め、前回のリベンジを誓うライシ司法権長のほか、サイード・モハンマド・ハタモルアンビア前総裁やレザイ公益評議会書記、デフガーン軍需産業担当最高指導者顧問などの革命防衛隊出身者、ザルガミ元国営放送総裁など、興味深い背景の候補者が名を連ねている(注9)。改革派・穏健派陣営は、本命だったザリーフ外相不在の中、ジャハンギリ第一副大統領に加え、“アーガーザーデ”の一人である故ラフサンジャニ師の長男:ハシェミ・テヘラン市評議会議長などが立候補している。
(注9:革命防衛隊などの過去の出身母体が必ずしもゆかりのある候補を支持している訳ではないことに留意が必要。穏健派に近いと考えられる候補であるラリジャニ最高指導者顧問は革命防衛隊出身かつ国営放送総裁も長年勤めた経歴がある。)
過去四半世紀のトレンドを見ると、改革を求める国民の渇望によって誕生したハタミ大統領(改革派)以降、イランの政権は、人々の現状打破への期待とそれが裏切られたことへの失望のサイクルを背景に、改革派・穏健派と強硬派の間をスイングしており、順当に行けば次は強硬派が政権を奪取する番である。大統領選挙の前哨戦とも呼ばれる国会議員選挙(昨年2月)でも、強硬派が圧勝しており、また、最近の国営放送の世論調査でも、国民の51%が「投票しない」と答えているなど、強硬派に有利な条件が揃っている。
これまで、一般に、組織力・動員力で上回る強硬派に対し、改革派・穏健派は、SNSなどをより積極的に駆使することで草の根の支持を獲得し、浮動票を掘り起こす構図であった。改革派・穏健派がコロナ禍の「空中戦」を制して「風」を呼び、この逆境をひっくり返せるのか、それとも強硬派がこのまま押し切るのか。ネット空間が主戦場となると見られるので、是非日本からも注目していただきたい。
(寄稿:角 潤一(在イラン日本国大使館 一等書記官)、編集・デザイン:深山 周作)